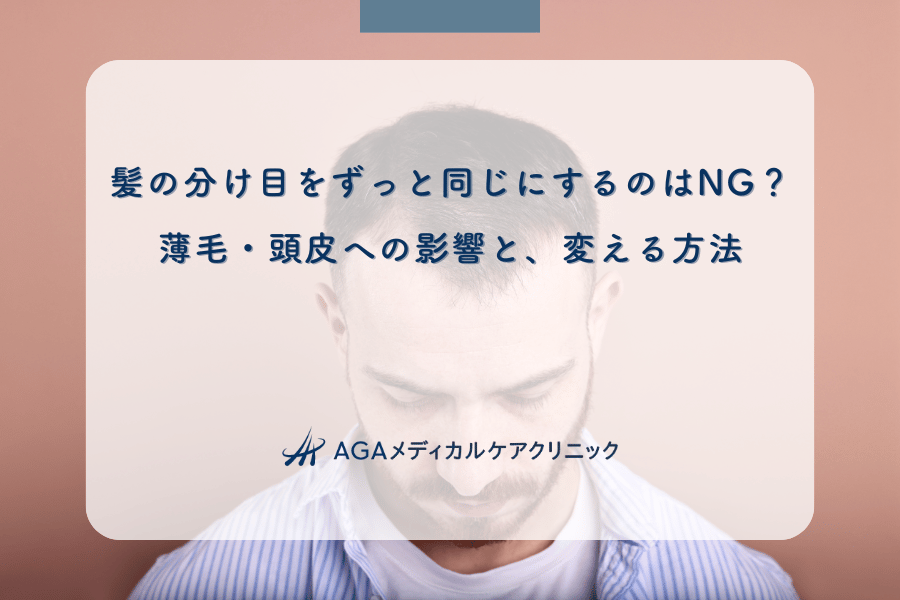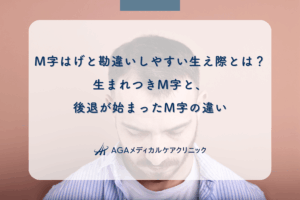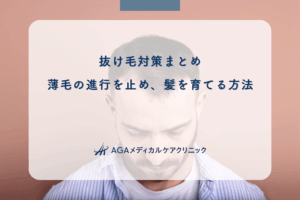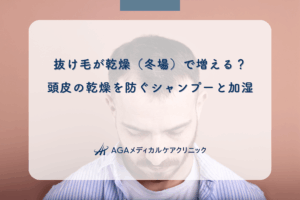「最近、髪の分け目が目立ってきた気がする」「いつも同じ分け目にしているけれど、これって頭皮に悪いのかな?」そんな風に感じていませんか。
髪の分け目は、その人の印象を左右するだけでなく、実は頭皮の健康状態とも深く関わっています。もし長年同じ分け目を続けているなら、知らず知らずのうちに頭皮に負担をかけているかもしれません。
この記事では、なぜ同じ分け目を続けるのが良くないのか、薄毛や頭皮への具体的な影響、そして今日からできる分け目を変える簡単な方法まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪の分け目」が目立つと感じる瞬間
普段はあまり意識していなくても、ふとした瞬間に「髪の分け目が目立つ」と感じることがあります。それは、頭皮からの何かしらのサインかもしれません。
多くの人が経験する、分け目が気になる瞬間を見ていきましょう。
鏡で真正面から自分を見たとき
毎日見ているはずの鏡。しかし、ある日ふと、分け目部分の地肌が以前より広く見えたり、くっきりと目立ったりすることに気づきます。
特に、洗面所の明るい照明の下では、その変化が顕著に感じられることがあります。髪全体のボリュームが減ったように感じ、不安を覚える最初の瞬間かもしれません。
エレベーターや電車内での他人の視線
他人との距離が近くなる空間では、視線が気になりがちです。
特にエレベーターで自分より背の高い人に囲まれた時や、電車の座席に座っている時に、上からの視線が自分の頭頂部、つまり分け目に集まっているように感じることがあります。
この感覚が、分け目への意識を高めるきっかけになります。
写真や動画に映った自分を見たとき
自分で鏡を見る角度とは違い、他人から撮影された写真や動画は、客観的な自分の姿を映し出します。
特に、屋外の太陽光の下や、フラッシュを使った撮影では、分け目部分が光を反射して白く目立つことがあります。
自分のイメージしていた姿とのギャップに驚き、対策を考え始める人も少なくありません。
ヘアスタイリングがうまくいかない時
以前は簡単に決まっていたヘアスタイルが、最近うまくいかない。特に分け目部分の髪がぺたっとしてしまい、ボリュームが出にくくなったと感じる時です。
髪の毛一本一本のハリやコシが失われ、分け目部分で髪が立ち上がらなくなることで、地肌が透けて見えやすくなり、分け目が目立つと感じるようになります。
なぜ同じ分け目は良くないのか?頭皮への影響
長期間、髪の分け目を同じ位置にし続けることは、見た目の問題だけでなく、頭皮環境にもさまざまな影響を与える可能性があります。特定の場所に負担が集中することが、主な原因です。
紫外線によるダメージの集中
頭皮は、顔の皮膚よりも多くの紫外線を浴びていると言われます。髪の毛がある程度のバリアになりますが、分け目部分は地肌が直接露出しています。
同じ分け目を続けていると、その部分だけが集中的に紫外線を浴び続けることになります。
紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こす(日焼け)だけでなく、毛根にある毛母細胞の働きを低下させる原因にもなります。
これが頭皮の老化を早め、健康な髪の育成を妨げる一因となり得ます。
分け目部分への紫外線ダメージ
| 影響の種類 | 具体的な内容 | 頭皮への懸念 |
|---|---|---|
| 乾燥 | 紫外線の熱により頭皮の水分が奪われる。 | フケやかゆみの原因になる。 |
| 炎症(日焼け) | 頭皮が赤くなる、ヒリヒリする。 | 頭皮環境が悪化し、抜け毛につながる。 |
| 光老化 | コラーゲンが破壊され、頭皮が硬くなる。 | 血行不良や毛根への栄養不足。 |
物理的な牽引(けんいん)による負担
髪には重さがあります。特に髪が長い人の場合、分け目を境にして左右に垂れ下がる髪の重みが、常に分け目部分の毛根にかかり続けます。
また、ポニーテールや特定の髪型で強く引っ張る習慣があると、その負担はさらに大きくなります。この継続的な物理的負担は「牽引性脱毛症」と呼ばれる抜け毛の原因になることも。
同じ場所ばかりに負担がかかることで、その部分の毛根が弱り、髪が細くなったり抜けやすくなったりする可能性があります。
血行不良の懸念
頭皮が紫外線のダメージを受けたり、物理的な牽引で常に緊張状態にあったりすると、その部分の血行が悪くなることが懸念されます。髪の毛は、毛根にある毛細血管から栄養を受け取って成長します。
血行不良に陥ると、毛母細胞に必要な栄養素や酸素が十分に行き渡らなくなります。その結果、髪の成長サイクルが乱れ、健康な髪が育ちにくくなる可能性があります。
頭皮の乾燥とバリア機能低下
分け目部分は、紫外線だけでなく、外気やエアコンの風などにもさらされやすい場所です。
これにより、頭皮の水分が蒸発しやすくなり、乾燥を招きます。頭皮が乾燥すると、外部の刺激から守る「バリア機能」が低下します。
バリア機能が低下した頭皮は、シャンプーの洗浄成分や花粉、ホコリなどのわずかな刺激にも敏感に反応しやすくなり、かゆみや炎症を引き起こす悪循環に陥ることがあります。
分け目と薄毛(AGA)の直接的な関係は?
「分け目が目立つ=薄毛(AGA)が始まった」と直結して考えてしまう人もいますが、両者の関係性を正しく理解することが大切です。
分け目が薄毛の原因ではない
まず明確にしておきたいのは、「同じ分け目を続けたこと」が、AGA(男性型脱毛症)の直接的な引き金になるわけではない、という点です。
AGAは、主に男性ホルモン(DHT:ジヒドロテストステロン)の影響や遺伝的要因によって、髪の成長サイクルが短くなり、髪が細く短くなっていく症状です。
前述の通り、同じ分け目は頭皮環境を悪化させ、抜け毛や髪のハリ・コシ低下の一因にはなります。しかし、それはAGAの発症とは別の問題です。
分け目が薄毛に見えやすくなる理由
では、なぜ分け目が目立つと薄毛が心配になるのでしょうか。それは、分け目部分の地肌が露出することで、「薄くなった」と視覚的に感じやすくなるためです。
また、AGAが進行し始めると、頭頂部(つむじ周り)や前頭部の髪が細く弱々しくなっていきます。
このAGAによる「髪の質の変化」と、長年の分け目による「クセ」や「頭皮ダメージ」が重なると、分け目部分の地肌がより一層目立ちやすくなり、「薄毛が進行した」と感じるようになるのです。
薄毛に見える要因の比較
| 要因 | 同じ分け目による影響 | AGAによる影響 |
|---|---|---|
| 髪の状態 | 分け目部分の毛根が弱り、ハリ・コシが失われやすい。 | 全体の髪(特に頭頂部・前頭部)が細く、短くなる。 |
| 地肌の見え方 | 特定のライン(分け目)の地肌が目立つ。 | 分け目だけでなく、その周辺の地肌も透けて見え始める。 |
| 主な原因 | 外的要因(紫外線、牽引、乾燥)。 | 内的要因(男性ホルモン、遺伝)。 |
AGAのサインを見逃さない
分け目が目立つと感じた時、それが単なる分け目のクセによるものか、あるいはAGAの初期症状なのかを見極めることが重要です。
AGAは進行性のため、早期の対策が鍵となります。分け目だけでなく、以下の点もチェックしてみましょう。
- 抜け毛に細くて短い毛が増えていないか
- 髪全体のハリやコシがなくなってきたか
- 生え際(特にM字部分)が後退していないか
- 頭頂部(つむじ)の地肌が透けて見えないか
これらに当てはまる場合、分け目の問題だけでなく、AGAの対策も視野に入れる必要があります。
自分の頭皮状態をセルフチェック
分け目を変える前に、まずは現在の頭皮状態を把握しましょう。特に分け目部分は、頭皮の健康状態が表れやすい場所です。
分け目部分の色
健康な頭皮は、透明感のある青白い色をしています。しかし、分け目部分が以下のような色になっている場合は注意が必要です。
頭皮の色でわかる健康サイン
| 頭皮の色 | 考えられる状態 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 青白い | 健康な状態 | 血行が良く、水分が保たれている。 |
| 赤い・ピンク色 | 炎症・日焼け | 紫外線ダメージ、シャンプーのすすぎ残し、刺激。 |
| 茶色・くすんだ黄色 | 血行不良・老化 | 紫外線の蓄積、代謝の低下、皮脂の酸化。 |
特に赤みがある場合は、何らかの炎症が起きているサインです。放置すると抜け毛の原因にもなるため、早めのケアが求められます。
頭皮の硬さ
頭皮の硬さも血行状態を知るバロメーターです。両手の指の腹を使って、頭頂部、側頭部、後頭部をそれぞれ動かしてみてください。
理想的なのは、側頭部や後頭部と同じように、頭頂部(分け目周辺)の頭皮も前後左右に動く状態です。
もし頭頂部の頭皮が硬く、あまり動かない場合は、血行が悪くなっているか、頭皮が張っている可能性があります。頭皮が硬いと、毛根に栄養が届きにくくなります。
フケやかゆみの有無
分け目周辺は乾燥しやすいため、フケやかゆみが出やすい場所でもあります。フケには種類があり、それぞれ原因が異なります。
フケの種類と主な原因
| フケの特徴 | 主な原因 | ケアの方向性 |
|---|---|---|
| カサカサした乾燥フケ | 頭皮の乾燥、洗浄力の強すぎるシャンプー | 保湿ケア、アミノ酸系シャンプーへの変更 |
| ベタベタした湿性フケ | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 | 皮脂バランスを整えるケア、食生活の見直し |
抜け毛の本数と質
シャンプー時や朝起きた時の抜け毛をチェックします。1日に50本から100本程度の抜け毛は自然な範囲内ですが、明らかに量が増えた場合は注意が必要です。
さらに重要なのが「抜け毛の質」です。
太くしっかりとした毛(寿命を全うした毛)が多いなら問題ありませんが、細く短い毛や、毛根部分が小さく弱々しい毛が多い場合は、髪が十分に成長する前に抜けてしまっているサインです。
これは分け目部分の頭皮環境の悪化、あるいはAGAの進行を示唆している可能性があります。
印象を変える!髪の分け目を変える簡単な方法
頭皮への負担を減らし、見た目の印象を変えるために、髪の分け目を定期的に変える習慣をつけましょう。
最初はクセがついていて変えにくいかもしれませんが、いくつかのコツを押さえれば簡単です。
ドライヤーでの乾かし方が鍵
分け目のクセをリセットする最大のチャンスは、髪を洗った後のドライヤー時です。髪は濡れている状態から乾く瞬間に形が決まります。
まずは、いつもと逆の方向に髪全体を流しながら乾かします。例えば、いつも左分けなら、右側に髪を全部持っていくように乾かします。
次に、前方や後方など、さまざまな方向から温風を当てて、髪の根元(地肌)をしっかりと乾かします。根元のクセがリセットされたら、新しい分け目を決め、最後に冷風を当ててスタイルを固定します。
この「根元を一度リセットする」作業が重要です。
スタイリング剤を上手に使う
新しい分け目にしても、髪のコシがないとすぐに元に戻ってしまいます。スタイリング剤を使って、新しい分け目の根元を立ち上げるサポートをしましょう。
ワックスやジェルを毛先につけるだけでなく、ボリュームアップ用のヘアスプレーやムースを根元付近に軽くつけます。
指の腹で頭皮をこすらないように注意しながら、根元に空気を入れるようになじませると、ふんわりとした立ち上がりが持続しやすくなります。
定期的に分け目を変える習慣
毎日変えるのが難しくても、「1ヶ月に1回、1cmだけずらす」というルールを決めるだけでも効果があります。
分け目を変えるテクニック例
| 方法 | ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 数cmずらす | いつもの分け目の隣に新しい分け目を作る。 | 最も簡単で、頭皮負担の分散が可能。 |
| センターパート(真ん中分け) | コームでまっすぐ分ける。 | 印象が大きく変わる。左右均等に。 |
| 逆サイドに変える | いつもと左右逆の分け目にする。 | 髪の立ち上がりが最も出やすい。 |
| ジグザグ分け | コームの先でジグザグに分ける。 | 地肌の露出が目立たなくなり、フワッとする。 |
コーム(櫛)を使った分け目の作り方
指でざっくり分けるのも自然で良いですが、最初はコームを使うと変えやすくなります。コームの先端(柄の部分)を使って、新しい分け目のラインを決めます。
この時、地肌を強くこすらないように注意しましょう。ラインを決めたら、ドライヤーの温風を根元に当て、コームの背で軽く押さえながらクセ付けすると、きれいな分け目が作りやすくなります。
分け目を変えることのメリット
分け目を変えることは、単に頭皮の負担を減らすだけでなく、見た目や気分にも良い影響をもたらします。
頭皮への負担を分散できる
最大のメリットは、これまで解説してきた「紫外線の集中」「物理的な牽引」「乾燥」といった頭皮へのダメージを分散できることです。
特定の部分だけが酷使される状態を防ぎ、頭皮全体の健康状態を保ちやすくなります。これにより、分け目部分の頭皮が赤くなったり、硬くなったりするのを防ぐ効果が期待できます。
髪のボリュームアップ効果
長年同じ分け目にしていると、髪はその方向に寝てしまうクセがついています。分け目をいつもと違う場所(特に逆サイド)に変えると、髪の根元がそのクセに逆らおうとして自然に立ち上がります。
これにより、特別なスタイリングをしなくても、髪全体のボリュームがアップしたように見えます。トップがふんわりすると、若々しい印象にもつながります。
手軽なイメージチェンジ
髪型を大きく変えなくても、分け目を変えるだけで顔の印象はかなり変わります。
例えば、いつも7:3分けの人がセンターパートにする、あるいは前髪を下ろしていた人が分け目を作っておでこを出すなど、少しの変化で気分転換にもなります。
新しい分け目が新しい自分の魅力を引き出してくれるかもしれません。
分け目ケアと同時に行いたい頭皮ケア
分け目を変えることは、頭皮環境を守る「守り」のケアです。同時に、頭皮環境をより良く改善する「攻め」のケアも行うことで、健康な髪を育てる土台が整います。
正しいシャンプーの方法
毎日のシャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とすために重要ですが、洗い方を間違えると逆効果になります。
シャンプー前には、まずブラッシングで髪のほつれを解き、ぬるま湯で頭皮と髪をしっかり予洗いします。シャンプーは手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。
洗う際は、爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく揉み洗いします。すすぎは最も重要で、分け目部分や生え際に泡が残らないよう、時間をかけて念入りに行います。
頭皮マッサージによる血行促進
頭皮が硬いと感じる人は、頭皮マッサージを取り入れましょう。血行を促進し、毛根に栄養を届きやすくします。
シャンプー中に行うか、育毛剤をつけた後に行うのが効果的です。指の腹で頭皮全体を掴むようにし、「下から上へ」引き上げるイメージで揉みほぐします。
気持ち良いと感じる程度の力加減で、毎日数分間続けることが大切です。
頭皮ケアの基本となる生活習慣
| ケアの種類 | 目的 | 日々の実践ポイント |
|---|---|---|
| 正しいシャンプー | 頭皮環境の清浄化 | 指の腹で洗い、すすぎを徹底する。 |
| 頭皮マッサージ | 血行促進 | 毎日数分、頭皮を引き上げるように行う。 |
| バランスの良い食事 | 髪への栄養補給 | タンパク質、ビタミン、ミネラルを意識する。 |
バランスの取れた食生活
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。健康な髪を育てるためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。
- タンパク質(髪の主成分):肉、魚、卵、大豆製品
- 亜鉛(髪の合成を助ける):牡蠣、レバー、牛肉
- ビタミンB群(頭皮の代謝を促す):豚肉、マグロ、レバー、納豆
これらを偏りなく摂取し、脂っこい食事やインスタント食品は控えるように心がけましょう。
育毛剤の活用
分け目が目立つ、髪のハリ・コシがなくなってきたと感じる場合、育毛剤の使用も有効な選択肢です。
育毛剤には、頭皮の血行を促進したり、毛母細胞の働きを活発にしたり、頭皮の炎症を抑えたりする成分が含まれています。
分け目を変える習慣や頭皮マッサージと併用することで、頭皮環境を総合的に整え、抜け毛の予防や健やかな髪の育成をサポートします。
自分の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌など)に合った育毛剤を選び、継続して使用することが重要です。
Q&A
- 分け目はどれくらいの頻度で変えるべきですか?
-
毎日変えるのが理想的ですが、現実的には難しいかもしれません。
まずは「シャンプーのたびに変える」「週末だけ変える」「1ヶ月に1回、1cmずらす」など、ご自身が続けやすいルールを見つけることが大切です。
同じ状態が数ヶ月以上続かないように意識するだけでも、頭皮への負担は大きく変わってきます。
- 分け目を変えたら、薄くなった部分の髪は生えてきますか?
-
分け目を変えることは、頭皮環境を改善し、健康な髪が育つ「土台」を整えることにつながります。
紫外線や物理的負担が原因で弱っていた毛根が元気を取り戻し、髪にハリやコシが戻る可能性はあります。
ただし、分け目を変える「だけ」で、AGA(男性型脱毛症)が治ったり、失われた髪が全て生えたりするわけではありません。薄毛の原因がAGAである場合は、専門の対策が必要です。
- 髪のクセが強くて、分け目が変えにくいのですが、どうすればいいですか?
-
最も重要なのは、髪が濡れている状態から直すことです。乾いた髪にいくらドライヤーを当てても、表面的なクセしか直りません。
シャンプー後、タオルドライした状態で、まず新しい分け目にしたい方向と「逆」に乾かし、根元のクセをリセットします。
その後、新しい分け目を作って再度ドライヤー(温風→冷風)を当てて固定します。最初は戻りやすいですが、これを数週間続けると、徐々に新しい分け目が定着しやすくなります。
- 分け目がくっきりついてしまう(割れてしまう)原因は?
-
主な原因は「長年のクセ」です。しかし、それ以外にも「髪のハリ・コシの低下」が考えられます。
髪が細く弱くなると、根元で立ち上がる力を失い、重力に負けてぺたんと寝てしまい、地肌が見えやすくなります。
また、「頭頂部のつむじ」の流れによって、元々割れやすい髪の生え方をしている場合もあります。
対策としては、分け目を変えること、根元を立ち上げるスタイリング、そして育毛剤などで髪のハリ・コシを育てるケアが有効です。
Reference
SAMRAO, Aman; MCMICHAEL, Amy; MIRMIRANI, Paradi. Nocturnal traction: techniques used for hair style maintenance while sleeping may be a risk factor for traction alopecia. Skin Appendage Disorders, 2021, 7.3: 220-223.
BILLERO, Victoria; MITEVA, Mariya. Traction alopecia: the root of the problem. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2018, 149-159.
OKORO, Obumneme Emeka; IMAM, Abubakar; BARMINAS, Rachel. Knowledge of traction alopecia and hair care practices among adolescents in Keffi, North-Central Nigeria. Skin appendage disorders, 2022, 8.2: 129-135.
SHARQUIE, Khalifa E., et al. Traction alopecia: clinical and cultural patterns. Indian Journal of Dermatology, 2021, 66.4: 445.
NZENG, Letitia Fiona Mbussuh, et al. Factors associated with traction alopecia in women living in Yaoundé (Cameroon). BMC Women’s Health, 2023, 23.1: 577.
KHUMALO, Nonhlanhla P., et al. Determinants of marginal traction alopecia in African girls and women. Journal of the American Academy of Dermatology, 2008, 59.3: 432-438.
AYANLOWO, Olusola Olabisi; OTROFANOWEI, Erere. A community-based study of hair care practices, scalp disorders and psychological effects on women in a Suburban town in Southwest Nigeria. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2023, 30.1: 53-60.
AFIFI, Ladan; OPARAUGO, Nicole C.; HOGELING, Marcia. Review of traction alopecia in the pediatric patient: Diagnosis, prevention, and management. Pediatric Dermatology, 2021, 38: 42-48.
SPERLING, Leonard C. Evaluation of hair loss. Current problems in Dermatology, 1996, 8.3: 99-136.