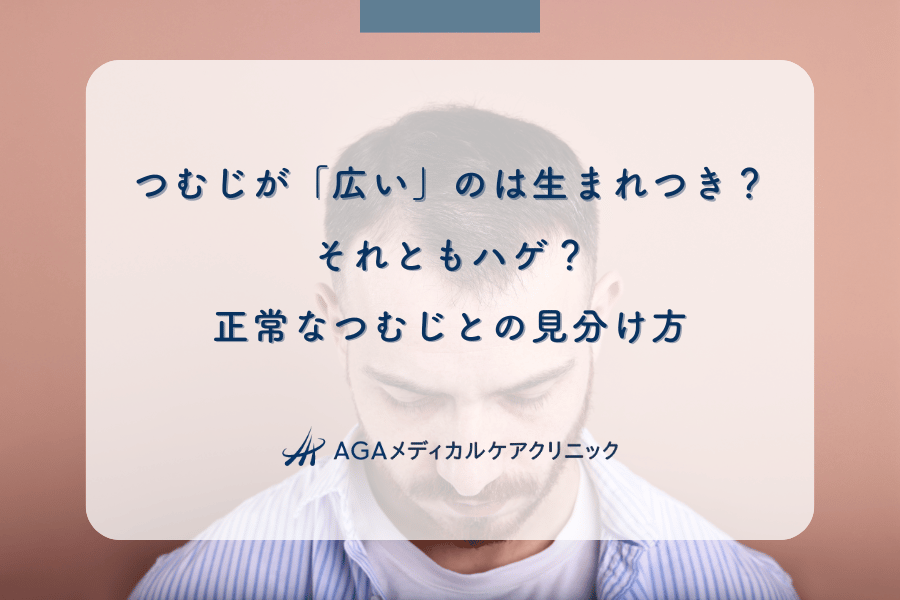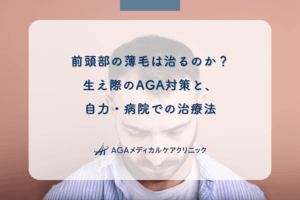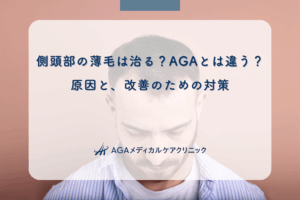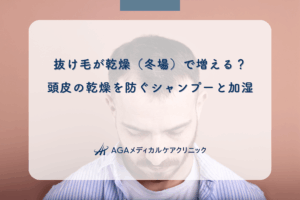ふと鏡を見たときや、人から指摘されたとき、「自分のつむじは広いのではないか?」と不安に感じた経験はありませんか。
つむじの広さは個人差が大きく、生まれつき広い人もいれば、薄毛のサインとして地肌が目立ってきている人もいます。
この記事では、「つむじが広い」と感じる原因、正常なつむじと薄毛が疑われるつむじの見分け方、そして気になり始めたときにできるセルフチェックや対策について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
つむじが「広い」と感じる主な理由
つむじが広く見える原因は一つではありません。生まれ持った特性である場合もあれば、後天的な要因が関係している場合もあります。
ご自身のつむじがなぜ広く見えるのか、その理由を探ることは、不安を解消し、適切な対応を考える上で重要です。
生まれつきの頭皮の特性
人によって肌の色や髪質が違うように、つむじの大きさや形、地肌の見え方にも生まれつきの個人差があります。
例えば、頭皮がもともと白い人は、髪の黒さとのコントラストで地肌が目立ちやすく、つむじが広く見えることがあります。また、つむじのうずまきの直径がもともと大きい場合もあります。
これらはその人の個性であり、必ずしも薄毛が進行しているわけではありません。
髪の毛の生え方やつむじの位置
髪の毛の生え方、特に毛流(もうりゅう)も、つむじの目立ち方に関係します。髪の毛が直毛で太い人は、髪が立ち上がりやすく、毛流に逆らうと地肌が見えやすくなることがあります。
逆もまた然りで、髪が細く柔らかい(猫っ毛)人は、髪が寝てしまい地肌に張り付くことで、透けて広く見えることもあります。
また、つむじが頭頂部のやや後ろにある場合、鏡で確認しにくく、ある日突然「広くなった」と感じることもあるようです。
加齢による髪質の変化
年齢を重ねると、髪の毛一本一本が細くなる傾向があります。これは「菲薄化(ひはくか)」と呼ばれます。髪の毛が細くなると、同じ本数でも全体のボリュームが減少し、地肌が透けやすくなります。
その結果、以前よりもつむじが広く見えるようになることがあります。これは薄毛の初期段階である可能性もありますが、加齢による自然な変化の一部とも考えられます。
頭皮環境の影響
頭皮の環境が悪化すると、髪の健やかな成長が妨げられ、つむじが目立つ原因になることがあります。例えば、皮脂の過剰分泌、乾燥、フケ、かゆみなどがある場合、頭皮に炎症が起きているかもしれません。
炎症が続くと毛根がダメージを受け、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりして、結果的につむじ周りが薄く見えることにつながります。
正常なつむじと薄毛(ハゲ)が疑われるつむじの違い
「つむじが広い」と感じたとき、最も知りたいのは「これが正常な範囲なのか、それとも薄毛のサインなのか」ということでしょう。
ここでは、両者を見分けるための具体的な特徴を解説します。
正常なつむじの特徴
まずは、心配のない正常なつむじの状態を知ることが大切です。ご自身のつむじと見比べてみてください。
地肌の見える範囲
正常なつむじは、うずまきの中心部分の地肌が見えますが、その範囲は比較的限定的です。地肌の色は青白いか、健康的な肌色をしています。
地肌が赤みを帯びていたり、広範囲にわたって透けて見えたりする場合は、少し注意が必要かもしれません。
つむじ周りの毛髪の状態
つむじ周りの髪の毛が、他の部分(側頭部や後頭部など)の髪の毛と同じくらいの太さやハリ・コシを持っている場合、正常である可能性が高いです。
うずまきに沿って、髪がしっかりと生えている状態です。
うずまきの明瞭さ
健康なつむじは、毛流による「うずまき」がはっきりと確認できます。中心から外側に向かって、髪が規則正しく流れているのが特徴です。
注意が必要なつむじの状態 (薄毛のサイン)
次に、薄毛が進行している可能性が疑われるつむじの特徴を挙げます。これらのサインが複数当てはまる場合は、早めのケアを検討しましょう。
地肌の透け感が目立つ
以前と比べて、つむじを中心とした地肌の見える範囲が明らかに広がってきた、あるいは地肌が透けて見えるようになったと感じる場合、注意が必要です。
特に、つむじのうずまきの外側まで地肌が目立つようであれば、毛量が減少している可能性があります。
つむじ周りの毛が細く短い
つむじ周辺の髪の毛が、他の部分の髪と比べて明らかに細い、短い、またはフワフワとした産毛のようになっている場合、これは薄毛の典型的なサインです。
ヘアサイクル(毛周期)が乱れ、髪が十分に成長しきる前に抜け落ちている(または細いまま成長が止まっている)可能性を示唆しています。
つむじのうずまきがぼやけている
髪の毛の密度が低下し、一本一本が細くなると、これまでハッキリしていたつむじの「うずまき」の境界線があいまいになり、ぼんやりとした印象になります。
うずまきがどこにあるのか分かりにくくなったと感じたら、それも一つのサインです。
正常なつむじと注意が必要なつむじの比較
| チェック項目 | 正常なつむじ | 注意が必要なつむじ |
|---|---|---|
| 地肌の状態 | 中心部のみ見える。色は青白いか肌色。 | 広範囲に透けて見える。赤みや茶色っぽさがあることも。 |
| 髪の太さ | 他の部分と同様の太さ・ハリがある。 | 細く、短く、弱々しい毛が目立つ。 |
| うずまきの形 | うずまきが明瞭に確認できる。 | うずまきの境界があいまい、ぼやけている。 |
つむじが広いのは生まれつきかハゲかを見分けるポイント
正常な状態と注意が必要な状態の違いを踏まえ、ご自身のつむじが「生まれつき」のものなのか、それとも「薄毛の進行」によるものなのかを判断するための、より具体的な見分け方を紹介します。
遺伝的要因とつむじの広さ
つむじの広さや薄毛のなりやすさには、遺伝的な要因が関わることが知られています。特にAGA(男性型脱毛症)は、遺伝的素因が強く影響します。
ご家族、特に父方・母方の祖父や父親の頭髪の状態を思い返してみてください。もしご親族に薄毛の方がいる場合、ご自身のつむじの広がりも遺伝的要因が関係している可能性が考えられます。
ただし、遺伝的素因があるからといって必ず薄毛になるわけではありませんし、逆に素因がなくても薄毛になることもあります。あくまで判断材料の一つと考えましょう。
成長過程での変化を振り返る
過去の写真、特に学生時代や10代、20代の頃の写真と、現在のつむじの状態を比較してみることは非常に有効です。
もし昔からつむじが広く、地肌が見えやすい状態であったなら、それは「生まれつき」の特性である可能性が高いです。
一方で、数年前の写真と比べて明らかに地肌の見える範囲が広がっている、髪が細くなっていると感じる場合は、薄毛が進行している可能性を考慮する必要があります。
他の薄毛サインとの比較
つむじの広がりが薄毛によるものか判断に迷うときは、つむじ以外の部分にも薄毛のサインが出ていないかを確認します。
生え際の状態
AGA(男性型脱毛症)は、つむじ(頭頂部)だけでなく、生え際(特にM字部分)から進行することも多いです。
生え際が以前より後退してきた、またはM字部分の剃り込みが深くなったと感じる場合、つむじの広がりもAGAの一環である可能性が高まります。
全体的なボリューム感
髪をセットするときに、以前よりボリュームが出にくくなった、髪全体のハリやコシが失われた、と感じることはありませんか。
これも髪が細くなっているサインであり、つむじの薄毛と連動している可能性があります。
抜け毛の量
シャンプー時や朝起きたときの枕元の抜け毛の量を意識してみましょう。明らかに抜け毛が増えたと感じる場合、ヘアサイクルが乱れている証拠かもしれません。
特に、細くて短い抜け毛が多い場合は注意が必要です。
薄毛のサインセルフチェック
| チェック部位 | 確認するポイント | 薄毛の可能性 |
|---|---|---|
| 生え際 | 以前より後退した。M字部分が深くなった。 | 高い |
| 髪全体 | ボリュームが出にくい。ハリ・コシがなくなった。 | 中〜高い |
| 抜け毛 | 量が増えた。細く短い毛が多い。 | 高い |
なぜつむじ周りから薄毛が目立ちやすいのか
薄毛の悩みにおいて、つむじ(頭頂部)と生え際は特に目立ちやすい部位です。なぜ、つむじ周りは薄毛の影響を受けやすいのでしょうか。その背景にはいくつかの理由があります。
頭皮の血流と栄養供給
頭頂部は、心臓から送られてくる血液が最後に到達しやすい部位の一つです。もともと毛細血管が細く、血流が滞りやすい傾向があります。
血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な酸素や栄養素が毛根(毛母細胞)まで十分に行き渡りにくくなります。その結果、髪が細くなったり、成長が妨げられたりして、薄毛につながりやすくなります。
皮脂分泌と頭皮環境
頭頂部は、皮脂腺(皮脂を分泌する腺)が多く存在する部位でもあります。皮脂は頭皮を乾燥から守るバリア機能の役割を果たしますが、分泌が過剰になると問題を引き起こします。
余分な皮脂が毛穴に詰まったり、酸化して炎症を引き起こしたりすると、頭皮環境が悪化し、抜け毛や薄毛の原因となることがあります。
AGA(男性型脱毛症)の影響
男性の薄毛の最も一般的な原因であるAGA(男性型脱毛症)は、特につむじ(頭頂部)と生え際に強く影響します。
AGAとは何か
AGAは、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、頭皮に存在する「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることで引き起こされます。
このDHTが毛根にある受容体と結合すると、髪の成長期を短縮させ、髪が太く長く成長する前に抜け落ちるように指令を出してしまいます。
つむじ(頭頂部)への影響
このAGAの原因となる酵素「5αリダクターゼ」や、DHTを受け取る「男性ホルモン受容体」は、主に前頭部(生え際)と頭頂部(つむじ)に多く存在しています。
そのため、AGAが発症すると、これらの部位から選択的に薄毛が進行していくのです。つむじが広いと感じる背景に、このAGAが潜んでいる可能性は十分に考えられます。
つむじの広さが気になり始めた時のセルフチェック
「もしかして薄毛が始まっているかも?」と感じたら、まずはご自身の現在の状態を客観的に把握することが大切です。
簡単なセルフチェック方法を紹介しますので、定期的に確認してみましょう。
鏡を使った確認方法
つむじは自分では直接見えにくいため、鏡を効果的に使う必要があります。
合わせ鏡でのチェック
洗面台の鏡など正面の鏡に向かい、手鏡を持って頭頂部を映します。つむじの地肌の色、毛の太さ、うずまきの状態をじっくりと観察します。
このとき、部屋の照明が明るすぎると実際より地肌が目立って見えることがあるため、自然光や普段生活している明るさで確認するのがよいでしょう。
スマートフォンでの撮影比較
最も客観的で、変化を追いやすい方法がスマートフォンでの撮影です。頭の真上から、つむじがはっきりと写るように撮影します。
同じ場所、同じ明るさで、1ヶ月ごとなど定期的に撮影し、画像を比較してみましょう。
「なんとなく広がった気がする」という主観的な感覚ではなく、「明らかに地肌の見える面積が違う」といった客観的な変化に気づくことができます。
抜け毛の状態を確認する
シャンプー時の排水溝や、ドライヤー時、朝起きたときの枕元などを確認し、抜け毛の「量」と「質」をチェックします。
抜け毛の太さと長さ
抜け毛の中に、細くて短い、いわゆる「成長しきれていない毛」が多く混じっていないかを確認します。
太く長い毛(寿命を全うした毛)が多い場合は正常なヘアサイクルですが、細く短い毛が多い場合は、AGAなどによりヘアサイクルが短縮しているサインです。
枕や排水溝の抜け毛の量
一日50本~100本程度の抜け毛は正常範囲内です。
しかし、「明らかに以前より排水溝に溜まる量が増えた」「枕に付着する毛の数が目立つようになった」という場合は、抜け毛が増加傾向にあると考えられます。
頭皮の状態を触って確認する
頭皮環境は髪の健康の土台です。指の腹で頭皮を優しく触ってみましょう。
頭皮の色
鏡で確認できる範囲で頭皮の色を見ます。健康な頭皮は青白い色をしています。赤みがかっている場合は炎症、茶色っぽい場合は血行不良や乾燥が疑われます。
頭皮の硬さ
両手の指の腹で頭皮全体をつかむようにして、前後左右に動かしてみます。頭皮が硬く、あまり動かない場合は、血行不良や緊張状態にある可能性があります。
血流が悪いと、髪に栄養が届きにくくなります。
つむじが広いと感じた時に見直したい生活習慣
つむじの広がりが気になり始めた段階であれば、日々の生活習慣を見直すことで、頭皮環境を整え、薄毛の進行を緩やかにできる可能性があります。
髪の健康は、体全体の健康と密接に関連しています。
食生活の改善点
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。栄養バランスの偏った食事は、健康な髪の成長を妨げます。
髪の成長に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミン類 | 頭皮環境を整え、血行を促進する。(特にB群、C、E) | 緑黄色野菜、果物、玄米、豚肉 |
避けるべき食習慣
一方で、脂っこい食事やジャンクフード、糖分の多いお菓子や飲料の過剰摂取は控えましょう。これらは皮脂の分泌を過剰にし、頭皮環境を悪化させたり、血流を悪くしたりする原因となります。
外食が多い方も、できるだけバランスを意識したメニューを選ぶことが大切です。
睡眠の質と髪の健康
髪の成長は、睡眠中に活発になります。質の良い睡眠は、健やかな髪を育むために重要です。
成長ホルモンと睡眠時間
睡眠中、特に眠り始めてからの深いノンレム睡眠中に「成長ホルモン」が多く分泌されます。成長ホルモンは、体の細胞分裂を促し、毛母細胞の働きも活性化させます。
理想的には6時間〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝時間と起床時間をなるべく一定に保つことが望ましいです。
睡眠環境の整備
寝る直前までのスマートフォンの使用は、ブルーライトの影響で睡眠の質を低下させます。
就寝1時間前からはリラックスできる時間とし、部屋の照明を暗くしたり、静かな音楽を聴いたりするなど、スムーズに入眠できる環境を整えましょう。
ストレス管理の重要性
過度なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。これにより頭皮の血流が悪化し、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなります。
ストレスが頭皮に与える影響
ストレスは血流悪化だけでなく、ホルモンバランスの乱れや、皮脂の過剰分泌を引き起こすこともあります。慢性的なストレスは、つむじ周りの薄毛を悪化させる一因となり得ます。
リラックス方法の見つけ方
日常生活でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけることが重要です。
適度な運動、趣味の時間、入浴、友人との会話など、心身ともにリラックスできる時間を持つよう意識しましょう。
ストレス解消法の例
- 軽いジョギングやウォーキング
- 湯船にゆっくり浸かる
- 好きな音楽を聴く、映画を見る
正しいヘアケア方法
毎日のシャンプーが、逆に頭皮にダメージを与えている可能性もあります。ヘアケア方法を見直してみましょう。
シャンプーの選び方と洗い方
洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥や過剰な皮脂分泌を招くことがあります。
頭皮が乾燥しやすい、または敏感だと感じる方は、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーを選ぶとよいでしょう。洗う際は、爪を立てず、指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗います。
すすぎ残しは毛穴詰まりや炎症の原因になるため、シャンプー剤が残らないよう十分にすすぐことが大切です。
シャンプー時の注意点
| 項目 | 良い例 | 避けるべき例 |
|---|---|---|
| 洗い方 | 指の腹でマッサージするように洗う。 | 爪を立ててゴシゴシ洗う。 |
| すすぎ | ぬるま湯で時間をかけてしっかりすすぐ。 | 熱すぎるお湯。シャワーを短時間で済ませる。 |
| 乾燥 | タオルドライ後、ドライヤーで頭皮から乾かす。 | 自然乾燥(雑菌が繁殖しやすい)。 |
頭皮マッサージの試み
シャンプー中や入浴後など、頭皮が温まっているときに頭皮マッサージを行うのもよいでしょう。指の腹で頭皮全体を優しく動かし、血行を促進します。リラックス効果も期待できます。
つむじの薄毛対策として考えられること
生活習慣の見直しと並行して、より積極的な対策を取りたいと考える方もいるでしょう。ここでは、つむじの薄毛に対して考えられるいくつかの対策を紹介します。
育毛剤の使用
薄毛の進行予防や、今ある髪を健やかに育てたい場合、育毛剤の使用は一つの選択肢です。
育毛剤は、頭皮環境を整え、毛根に栄養を与え、血行を促進することなどを目的としています。
育毛剤の役割
育毛剤には様々な種類がありますが、多くは「頭皮の血行促進」「毛母細胞の活性化」「頭皮の抗炎症」「皮脂の過剰分泌抑制」などを助ける成分が含まれています。
これらにより、ヘアサイクルを正常に近づけ、抜け毛を予防し、髪の成長をサポートすることを目指します。
育毛剤の選び方のポイント
ご自身の頭皮の状態や悩みに合った成分が配合されているかを確認しましょう。例えば、血行促進を重視するのか、頭皮の乾燥や炎症を抑えたいのかによって、適した製品は異なります。
また、毎日継続して使用するものなので、価格や使用感(香り、べたつきなど)が自分に合うかも重要なポイントです。
育毛剤の主な目的と期待できること
| 主な目的 | 期待できること | 関連する成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進 | 毛根への栄養供給サポート。 | センブリエキス、ビタミンE誘導体など |
| 頭皮環境改善 | フケ・かゆみ・炎症の抑制。 | グリチルリチン酸2Kなど |
| 毛母細胞活性化 | 髪の成長サイクルのサポート。 | 独自成分、各種エキスなど |
継続使用の大切さ
育毛剤は、使用してすぐに髪が生えたり、太くなったりするものではありません。
ヘアサイクル(髪が生え変わる周期)を考えると、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は継続して使用することが必要です。
すぐに結果が出ないと諦めず、根気よくケアを続けることが重要です。
生活習慣見直しチェックリスト
- 栄養バランスの取れた食事
- 十分な睡眠時間の確保
- 適度な運動
- ストレスの溜めすぎ防止
専門機関への相談
セルフケアを続けても抜け毛が減らない、つむじの広がりが明らかに進行している、またはAGAの可能性が高いと感じる場合は、一人で悩み続けずに専門機関に相談することも検討しましょう。
皮膚科や専門クリニックの役割
皮膚科や薄毛治療を専門とするクリニックでは、医師が頭皮の状態や毛髪の状態を視診やマイクロスコープなどで詳しく診断します。
薄毛の原因がAGAなのか、他の皮膚疾患(脂漏性皮膚炎や円形脱毛症など)なのかを判断してもらえます。
相談するタイミング
「明らかに薄くなってから」ではなく、「気になり始めた」という早期の段階で相談することが、対策の選択肢を広げる上で望ましいです。
特に、抜け毛の急増や生え際の後退も同時に起きている場合は、早めの相談をお勧めします。
どのような検査や診断があるか
問診(生活習慣、家族歴など)に加え、マイクロスコープによる頭皮や毛穴の状態の確認、血液検査(ホルモン値や他の疾患の有無)、場合によっては遺伝子検査などを行うことがあります。
これらの結果に基づき、医師が現在の状態と原因、そして考えられる対策(生活指導、外用薬や内服薬の処方など)を提案します。
つむじはげの改善法まとめに戻る
つむじが「広い」ことに関するよくある質問
- つむじはいくつあるのが正常ですか?
-
つむじの数は、1つの人が最も一般的ですが、2つある人(「鳥居つむじ」などと呼ばれることもあります)や、まれに3つ以上ある人もいます。
つむじが2つあると、毛流が複雑になり、分け目ができやすくなったり、地肌が目立ちやすくなったりすることがありますが、それ自体は異常ではありません。生まれつきの個性の一つです。
- つむじが広いと将来必ずハゲますか?
-
生まれつきつむじが広いからといって、将来必ず薄毛(ハゲ)になるわけではありません。つむじの広さと薄毛の進行は、必ずしもイコールではありません。
ただし、以前と比べて明らかに広がってきた、髪が細くなった、抜け毛が増えたといった変化がある場合は、薄毛が進行しているサインの可能性があります。
現在の状態だけでなく、過去からの「変化」に注目することが重要です。
- 高校生でもつむじが広いのは薄毛の始まりですか?
-
高校生など10代の場合、多くは生まれつきの毛流や髪質によって広く見えているケースです。しかし、若年層でもAGA(男性型脱毛症)が発症することはあります。
もし、中学時代などと比べて急に広がりを感じたり、抜け毛が異常に増えたりした場合は、AGAの可能性もゼロではありません。
過度なダイエット、睡眠不足、強いストレスなども影響することがあるため、まずは生活習慣を見直してみることも大切です。
- つむじの薄毛は改善しますか?
-
つむじの薄毛の原因によります。
AGAが原因の場合、放置すると進行することが多いですが、適切な対策(育毛剤の使用、専門機関での治療など)を行うことで、進行を遅らせたり、毛髪の状態を良くしたりすることは期待できます。
生活習慣の乱れやストレスが一時的な原因であれば、それらを改善することで抜け毛が減り、状態が良くなることもあります。
早めに原因を特定し、ご自身に合ったケアを継続することが重要です。
Reference
CESARATO, Nicole, et al. Short anagen hair syndrome: association with mono-and biallelic variants in WNT10A and a genetic overlap with male pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2023, 189.6: 741-749.
SHIMOMURA, Yutaka. Congenital hair loss disorders: rare, but not too rare. The Journal of dermatology, 2012, 39.1: 3-10.
PHILLIPS III, J. Hunter; SMITH, Sharon L.; STORER, James S. Hair loss: common congenital and acquired causes. Postgraduate Medicine, 1986, 79.5: 207-215.
REDMOND, Leah C., et al. Male pattern hair loss: Can developmental origins explain the pattern?. Experimental Dermatology, 2023, 32.7: 1174-1181.
FITRIANI, Fitriani, et al. Diagnosis and Management of Hair Loss in Pediatric. Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, 2024, 36.2: 142-148.
KINOSHITA‐ISE, M., et al. Identification of factors contributing to phenotypic divergence via quantitative image analyses of autosomal recessive woolly hair/hypotrichosis with homozygous c. 736T> A LIPH mutation. British Journal of Dermatology, 2017, 176.1: 138-144.
AHMED, Azhar, et al. Genetic hair disorders: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.3: 421-448.
GONZALEZ, M. E.; CANTATORE‐FRANCIS, J.; ORLOW, S. J. Androgenetic alopecia in the paediatric population: a retrospective review of 57 patients. British Journal of Dermatology, 2010, 163.2: 378-385.
SPERLING, Leonard C. Evaluation of hair loss. Current problems in Dermatology, 1996, 8.3: 99-136.
HARRISON, Shannon; SINCLAIR, Rodney. Optimal management of hair loss (alopecia) in children. American Journal of Clinical Dermatology, 2003, 4.11: 757-770.