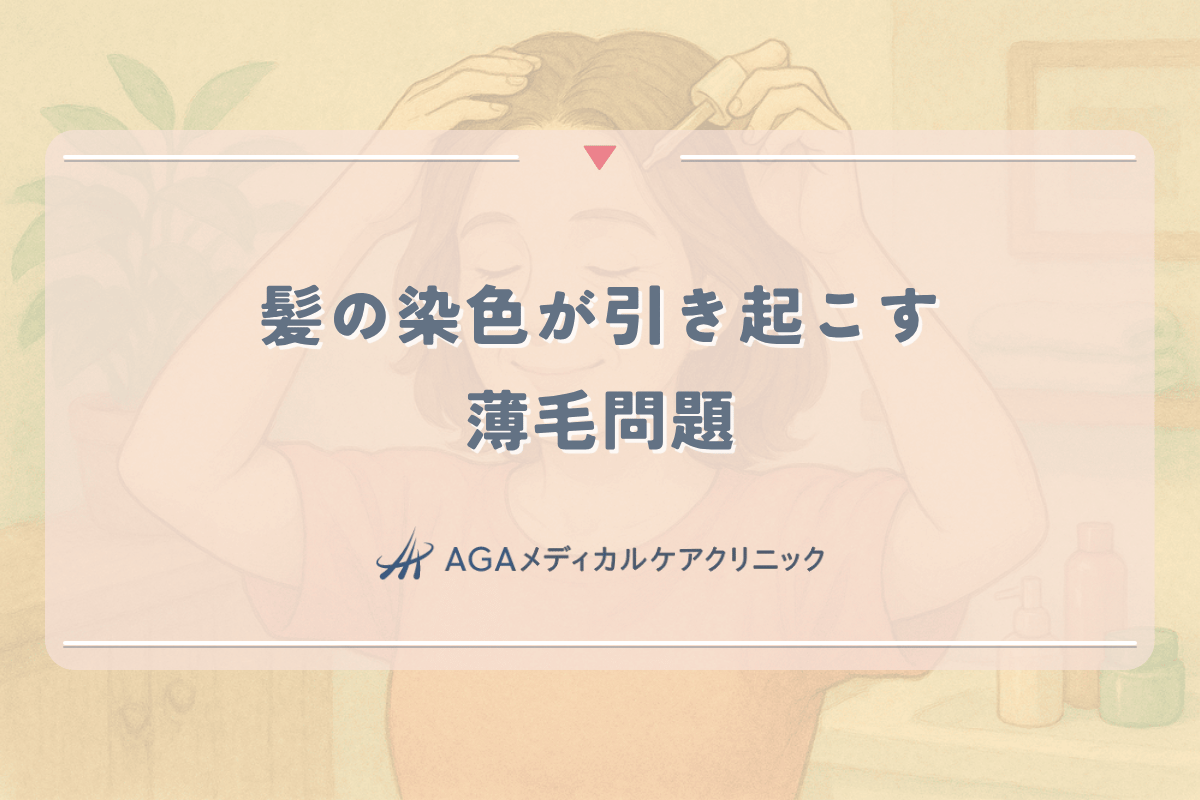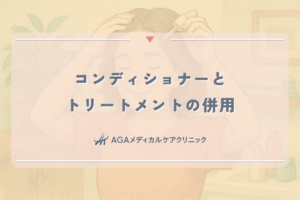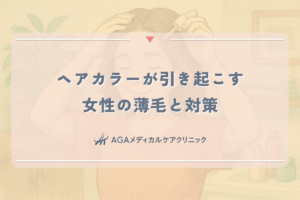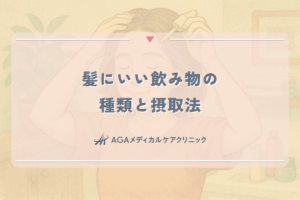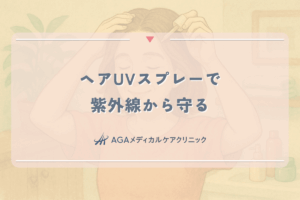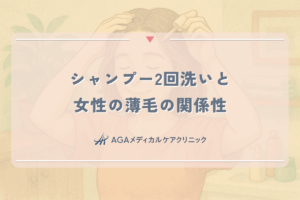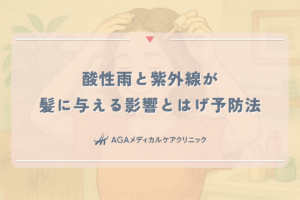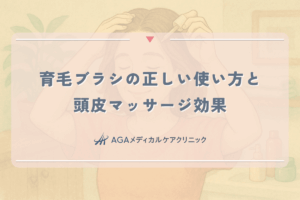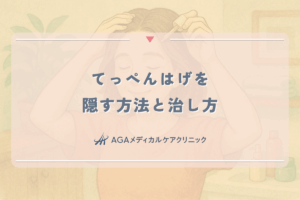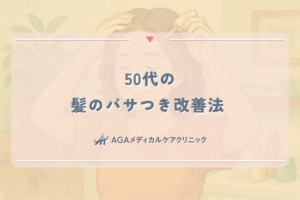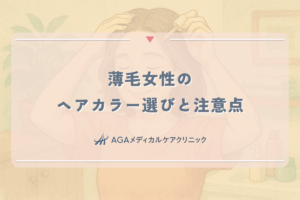「髪を染めたらはげるのでは?」という不安は、おしゃれを楽しみたい多くの女性が抱える共通の悩みのようです。
実際に、ヘアカラー後に抜け毛が増えたり、髪が細くなったりした経験から、髪染めと薄毛の関係を気にしている方も少なくありません。
この記事では、なぜ髪染めが薄毛の一因となり得るのか、その原因を科学的な視点から詳しく解説します。
そして、髪と頭皮の健康を守りながら、ヘアカラーと上手に付き合っていくための具体的な対策法を専門家の立場から紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ「髪を染めたらはげる」と感じるのか?
ヘアカラーを楽しんだ後に、ふと「髪が薄くなったかも」と感じる感覚は、気のせいではないかもしれません。
髪染めが直接的な原因でなくても、薄毛につながる複数の要因が潜んでいます。
ヘアカラー剤が頭皮に与える刺激
一般的なアルカリ性カラー剤には、髪の色素を抜いて染料を浸透させるために、アルカリ剤や過酸化水素といった化学物質が含まれています。
これらの成分は、髪だけでなく頭皮にとっても強い刺激物です。頭皮のバリア機能が低下している状態でカラー剤が付着すると、炎症やかゆみ、赤みを引き起こす場合があります。
この頭皮の炎症が、健康な髪が育つ土壌を損なう一因となるのです。
髪の主成分ケラチンへのダメージ
髪の約80%はケラチンというタンパク質で構成されています。ヘアカラー剤に含まれるアルカリ剤は、髪の表面を覆うキューティクルを開き、内部に染料を浸透させます。
この作用は、髪の内部構造に変化をもたらし、ケラチンタンパク質を破壊する場合があります。
ダメージを受けた髪はしなやかさや強度を失い、切れ毛や枝毛になりやすくなります。
根元から抜ける「抜け毛」だけでなく、途中から切れてしまう「切れ毛」が増えるのも、全体的に髪が薄くなったと感じる原因の一つです。
髪のダメージにつながる化学反応
| 成分 | 役割 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| アルカリ剤 | キューティクルを開く | 髪の膨潤、タンパク質の流出 |
| 過酸化水素 | メラニン色素の脱色 | 髪の乾燥、強度の低下 |
| 酸化染料 | 髪の内部で発色する | アレルギー反応のリスク |
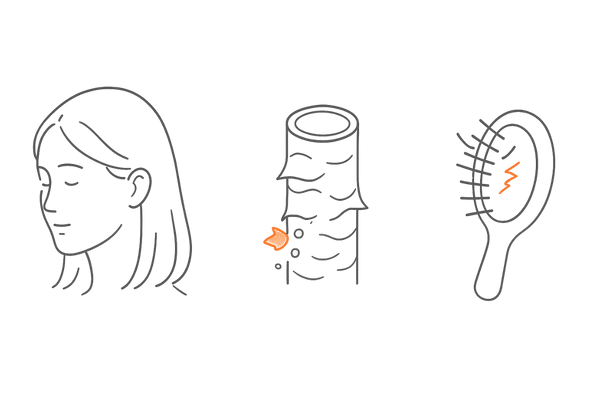
染髪後の不適切なヘアケア
髪染め後の髪は非常にデリケートな状態です。キューティクルが開き、内部の栄養分が流出しやすい状態になっています。
このタイミングで洗浄力の強いシャンプーを使ったり、ドライヤーの熱を当てすぎたりすると、ダメージをさらに加速させます。
染めた後のケアを怠ると、結果として髪の健康を損ない、薄毛の印象を強めてしまうのです。適切なアフターケアの知識を持つことが、髪を守る上で重要です。
髪染めではげる原因
「髪染めではげる」という現象は単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って起こります。
化学物質による頭皮への直接的な影響から、髪そのものの構造的なダメージまで、薄毛につながる主な原因を具体的に見ていきましょう。
接触性皮膚炎による頭皮環境の悪化
ヘアカラー剤に含まれるパラフェニレンジアミン(PPD)などの酸化染料は、アレルギー性接触皮膚炎の原因となる場合があります。
一度アレルギーを発症すると、その後もカラー剤を使用するたびに、かゆみや赤み、腫れや湿疹などの症状が現れます。
頭皮が慢性的な炎症状態に陥ると毛根にある毛母細胞の働きが阻害され、健康な髪の成長が妨げられます。
この頭皮環境の悪化が、抜け毛の増加や髪質の低下を招くのです。
頭皮トラブルのサイン
- 染めている最中や後に強いかゆみを感じる
- 頭皮が赤くなる、またはヒリヒリする
- フケやかさぶたが増える
- 湿疹やただれができる
髪のキューティクルの損傷と断毛
キューティクルは、髪の内部を守る鎧のような役割を果たしています。
しかし、ヘアカラーの化学反応によってこのキューティクルが剥がれたり、めくれたりすると、髪が無防備な状態になります。
具体的には、内部の水分やタンパク質が流出しやすくなり、髪が乾燥してパサパサになります。
強度が低下した髪はブラッシングやシャンプーといった日常的な刺激にも耐えられず、途中からプツリと切れてしまいます。
この「断毛」が積み重なると毛量が減少し、薄毛が進行したように見えてしまうのです。
毛周期(ヘアサイクル)への影響
髪の毛には、成長期、退行期、休止期というサイクルがあります。
健康な髪のほとんどは成長期(2~6年)にありますが、頭皮環境が悪化したり毛母細胞がダメージを受けたりすると、このサイクルが乱れます。
成長期が短縮され、髪が十分に成長しないまま退行期・休止期へと移行してしまうのです。その結果、細く短い毛が増え、全体のボリュームが失われていきます。
強い化学物質による刺激は、この正常な毛周期を乱す引き金となり得ます。
正常な毛周期と乱れた毛周期
| 期間 | 正常な毛周期 | 乱れた毛周期 |
|---|---|---|
| 成長期 | 2~6年(長く太く成長) | 数ヶ月~1年(短く細いまま) |
| 退行期 | 約2週間 | 期間は同様だが早く訪れる |
| 休止期 | 約3~4ヶ月 | 休止期の毛の割合が増加 |
薄毛につながりやすい染髪の習慣
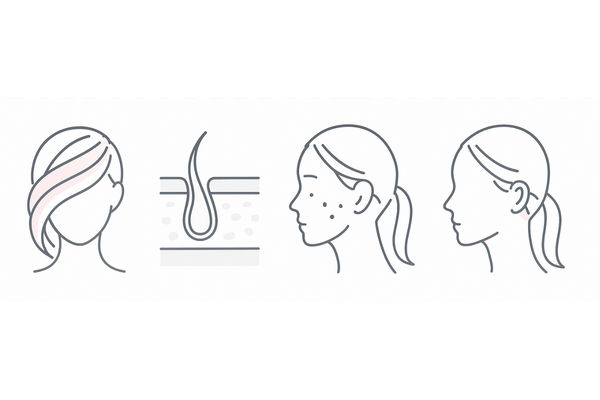
ヘアカラーが薄毛の一因になる可能性があるとはいえ、すべての人が同じ影響を受けるわけではありません。
特にこれから挙げるような習慣がある方は、髪や頭皮への負担が大きくなり、薄毛のリスクを高めている可能性があります。ご自身の習慣と照らし合わせて確認してみましょう。
高頻度のカラーリング
髪色の美しさを保つために1ヶ月に1回以上の頻度で髪全体を染めている場合、頭皮や髪が回復する時間がないまま、繰り返しダメージを受けることになります。
新しく生えてきた根元部分だけを染める「リタッチ」ではなく、毎回毛先まで染料を塗布していると、髪のダメージは深刻化します。
ダメージが蓄積した髪は細くなり、切れやすくなるため、薄毛が目立つ原因となります。
ブリーチ(脱色)の繰り返し
明るい髪色やビビッドな色合いを楽しむために必要なブリーチは、ヘアカラーの中でも特に髪への負担が大きい施術です。
ブリーチ剤は髪のメラニン色素を強力に分解するため、髪の内部構造を大きく破壊します。
複数回ブリーチを繰り返した髪はタンパク質が失われて強度が著しく低下し、少しの刺激で切れてしまうケースも珍しくありません。
頭皮に付着すれば、強い刺激となり炎症を引き起こすリスクも高まります。
自宅でのセルフカラーのリスク
手軽で費用を抑えられるセルフカラーですが、専門知識がないまま行うと多くのリスクが伴います。
薬剤の選定ミス、必要以上に長く放置してしまう、頭皮に薬剤をべったりと塗布してしまうなどが、深刻なダメージにつながります。
また、染めムラを直そうとして短期間に何度も染め直すといった悪循環に陥りやすいのも、セルフカラーの危険な点です。
セルフカラーの主なリスク
| リスクの種類 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 技術的な問題 | 薬剤の不均一な塗布、放置時間の間違い | 染めムラ、深刻な髪のダメージ |
| 保護の欠如 | 頭皮の保護をしない、薬剤のすすぎ残し | 頭皮の炎症、かぶれ |
| アレルギー | パッチテストを省略する | 突然のアナフィラキシーショックの危険性 |
アレルギー反応の無視
「少しピリピリするけど、いつもだから大丈夫」「かゆいけど我慢できる範囲」といったように、カラーリング中の軽いアレルギー反応を軽視している方も見受けられます。
その小さなサインは、体が発している危険信号です。無視して染髪を続けると症状が徐々に悪化し、ある日突然、顔が腫れ上がるような重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
頭皮の炎症は毛根にダメージを与え、抜け毛を誘発します。
ヘアカラー剤の種類と髪への影響度
一言でヘアカラーといっても、その種類はさまざまです。染まる仕組みや髪・頭皮への負担の度合いも異なります。
自分の目的や髪の状態に合わせて適切な種類を選ぶことが、ダメージを最小限に抑える鍵となります。
永久染毛剤(アルカリカラー)
美容室で一般的に使用される「おしゃれ染め」や「白髪染め」の多くがこのタイプです。
医薬部外品に分類され、1剤(アルカリ剤・酸化染料)と2剤(過酸化水素)を混ぜて使用します。
キューティクルを開いて髪の内部で染料を発色させるため、色持ちが良く、髪を明るくするのも可能です。
しかし、化学反応を伴うため、髪と頭皮への負担は最も大きい種類といえます。ジアミン系の染料を含むものが多く、アレルギーのリスクも考慮する必要があります。
半永久染毛料(ヘアマニキュア)
ヘアマニキュアやカラートリートメント、カラーリンスなどがこのカテゴリーに含まれます。化粧品に分類され、髪の表面を酸性の染料でコーティングするように染めます。
キューティクルを開かないため、髪や頭皮へのダメージはほとんどありません。髪にハリやコシを与える効果も期待できます。
ただし髪を明るくすることはできず、シャンプーのたびに色落ちし、持続期間は2~4週間程度と短いのが特徴です。汗や雨で色落ちし、衣服を汚す可能性もあります。
染毛剤の種類別比較
| 項目 | 永久染毛剤(アルカリカラー) | 半永久染毛料(ヘアマニキュア) |
|---|---|---|
| ダメージ | 大きい | 少ない |
| 持続期間 | 長い(1~2ヶ月) | 短い(2~4週間) |
| 髪を明るくする力 | ある | ない |

一時染毛料(カラースプレーなど)
カラースプレーやヘアマスカラのように、髪の表面に顔料を付着させるだけのタイプです。化粧品に分類されます。
シャンプーで簡単に洗い流せるため、1日だけ髪色を変えたい場合などに使用します。
髪や頭皮への負担は最も少ないですが、染毛効果は一時的です。ゴワつきや、雨・汗による色落ちには注意が必要です。
髪と頭皮を守る正しい髪染めの知識
髪染めによる薄毛のリスクを理解した上で、ダメージを最小限に抑えて安全にヘアカラーを楽しむためには、正しい知識を持っておきましょう。
美容室で染める重要性
セルフカラーに比べて費用はかかりますが、専門家である美容師による施術には、それを上回るメリットがあります。
美容師はあなたの髪質や現在のダメージレベル、頭皮の状態を診断し、適した薬剤を選定してくれます。
また、根元だけを染めるリタッチ技術や、頭皮に薬剤をつけないように塗布する「ゼロテク」など、専門的な技術でダメージを最小限に抑える工夫をしてくれます。
髪の悩みについて相談できる心強い存在でもあります。
パッチテストの徹底
パッチテストは、染毛剤によるアレルギー反応が起きないかを事前に確認するための重要なテストです。
これまで問題がなかった人でも、体質の変化によって突然アレルギーを発症する場合があります。
美容室で染める場合でも自宅で染める場合でも、毎回必ず染毛の48時間前に行う習慣をつけましょう。
この一手間が、深刻なアレルギーからあなた自身を守ります。
簡単なパッチテストの手順
- 実際に使用する染毛剤を少量混ぜ合わせる。
- 絆創膏などに染毛剤を塗り、腕の内側などの皮膚の柔らかい部分に貼る。
- 48時間様子を見て、かゆみ、赤み、腫れなどの異常がないか確認する。
染める前の頭皮ケア
カラーリング当日は、シャンプーをしないで行くのがおすすめです。頭皮の皮脂が天然の保護膜となり、カラー剤の刺激から頭皮を守ってくれます。
また、美容室によっては、カラーリング前に頭皮用の保護オイルやスプレーを塗布してくれるサービスもあります。
このようなオプションを活用するのも、頭皮を守るための有効な手段です。
染める頻度の適切な間隔
髪と頭皮への負担を考えると、カラーリングの頻度はできるだけ空けるのが理想です。
全体を染めるのは最低でも2~3ヶ月に1回程度に留め、その間は根元の白髪などが気になる場合でも、リタッチや部分的に使えるヘアマスカラなどで対応するのが良いでしょう。
髪が伸びる速さには個人差がありますが、適切な間隔を保つのが長期的に美しい髪を維持する秘訣です。
推奨される染髪頻度の目安
| 施術内容 | 推奨される頻度 | 理由 |
|---|---|---|
| 全体カラー | 2~3ヶ月に1回 | 毛先へのダメージ蓄積を防ぐため |
| リタッチ(根元染め) | 1~2ヶ月に1回 | 新生部のみに薬剤を塗布し負担を軽減 |
| ブリーチ | 最低でも3ヶ月以上空ける | 髪と頭皮への負担が非常に大きいため |
染めた後の髪を健やかに保つアフターケア

ヘアカラーは染めて終わりではありません。むしろ、染めた後のケアこそが、髪のコンディションを左右し、将来の薄毛リスクを低減させるために極めて重要です。
ダメージを受けて敏感になっている髪と頭皮を、どのようにケアすれば良いのかを見ていきましょう。
当日のシャンプーは避けるべきか
多くの美容室で、カラーリング当日のシャンプーは控えるようにアドバイスされます。これには二つの理由があります。
一つは、染料が髪の内部に完全に定着するには時間がかかり、すぐにシャンプーをすると色落ちしやすくなるためです。
もう一つは、カラー剤によってアルカリ性に傾いた髪と頭皮が、弱酸性の安定した状態に戻るのに時間が必要だからです。
少なくとも24時間はシャンプーを我慢すると色の持ちが良くなり、頭皮への負担も軽減できます。
保湿を重視したシャンプー・トリートメント選び
カラーリング後のヘアケア製品は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系や、保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が豊富に含まれたものを選びましょう。
また、カラーヘア専用の製品は色持ちを良くする成分や、アルカリ性に傾いた髪を弱酸性に戻す効果が期待できるためおすすめです。
シャンプー後は、必ずトリートメントで髪に栄養と潤いを補給し、キューティクルを整えると良いです。
ヘアケア製品選びのポイント
| 製品タイプ | 選ぶべき成分・特徴 | 避けるべき成分 |
|---|---|---|
| シャンプー | アミノ酸系洗浄成分、ヘマチン | 高級アルコール系(ラウレス硫酸Na等) |
| トリートメント | セラミド、コラーゲン、ケラチン | 特に無し(保湿成分を重視) |
頭皮マッサージによる血行促進
健康な髪は、健康な頭皮から生まれます。頭皮の血行が悪いと髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなります。
シャンプーの際や、お風呂上がりのリラックスタイムに、指の腹を使って優しく頭皮を動かすようにマッサージする習慣を取り入れましょう。
これによって頭皮の血行が促進され、リフレッシュ効果も期待できます。ただし、爪を立てて頭皮を傷つけないように注意してください。
紫外線から髪と頭皮を守る
紫外線は肌だけでなく、髪と頭皮にもダメージを与えます。特にカラーリング後の髪は、紫外線によって色が抜けやすくなったり、乾燥が進んだりします。
外出時には帽子や日傘、髪用のUVカットスプレーなどを活用して、紫外線対策を徹底しましょう。
頭皮が日焼けすると、炎症を起こして抜け毛の原因にもなるため、髪の分け目などにも注意が必要です。
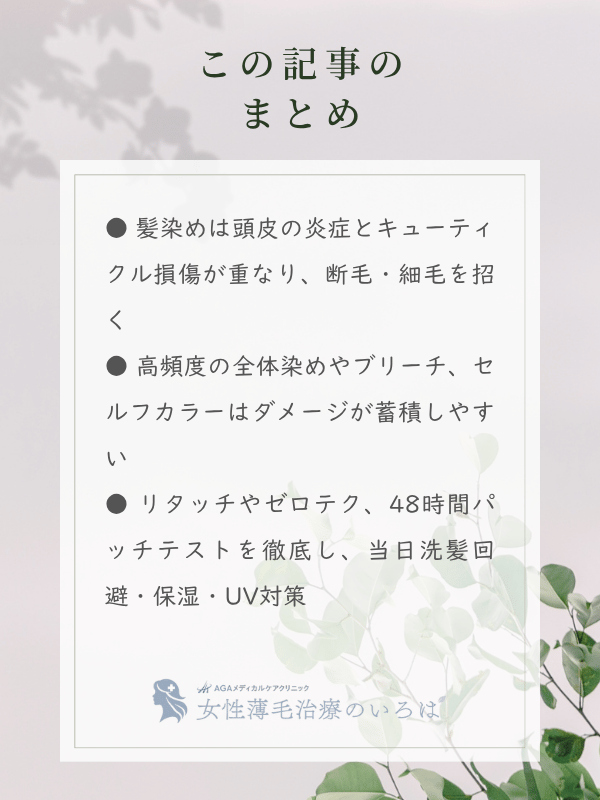
よくある質問
さいごに、髪染めと薄毛に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- ヘアマニキュアなら薄毛の心配はない?
-
ヘアマニキュアは髪の表面をコーティングするだけなので、アルカリカラーに比べて髪や頭皮へのダメージは格段に少なく、薄毛に直接つながるリスクは低いといえます。
しかし、頭皮にべったりと付着したまま放置すると毛穴を塞いでしまい、頭皮環境に影響を与える可能性はゼロではありません。
また、製品によってはアレルギーを引き起こす成分が含まれている場合もあるため、使用前のパッチテストが推奨されます。
- ヘナカラーは髪に優しい?
-
100%天然のヘナは植物由来の染料で髪へのダメージが少なく、トリートメント効果も期待できるため、髪に優しい選択肢の一つです。
ただし、染まる色がオレンジ系に限られる、染めるのに時間がかかるなどの特徴があります。
注意したいのは、「ケミカルヘナ」と呼ばれる製品です。
これらには発色を良くするためにジアミンなどの化学染料が添加されていることがあり、天然ヘナのつもりで使ってアレルギーを起こすケースがあります。成分表示をよく確認しましょう。
- 染めた後、どのくらいで抜け毛は落ち着く?
-
ヘアカラーによる一時的な頭皮の炎症や刺激が原因で抜け毛が増えた場合、頭皮環境が正常に戻れば、1~3ヶ月程度で抜け毛は落ち着くのが一般的です。
これは、毛周期における休止期の毛が抜けるタイミングと関連しています。
しかし、3ヶ月以上経っても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行しているように感じる場合は、アレルギーによる慢性的な炎症や、他の原因(AGA、ホルモンバランスの乱れなど)が隠れている可能性があります。
その際は自己判断で様子を見続けるのではなく、早めに専門クリニックへ相談しましょう。
参考文献
MOREL, Olivier JX; CHRISTIE, Robert M. Current trends in the chemistry of permanent hair dyeing. Chemical reviews, 2011, 111.4: 2537-2561.
HE, Yongyu, et al. Mechanisms of impairment in hair and scalp induced by hair dyeing and perming and potential interventions. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1139607.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
KIM, Ki-Hyun; KABIR, Ehsanul; JAHAN, Shamin Ara. The use of personal hair dye and its implications for human health. Environment international, 2016, 89: 222-227.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
KALIYADAN, Feroze, et al. Scanning electron microscopy study of hair shaft damage secondary to cosmetic treatments of the hair. International journal of trichology, 2016, 8.2: 94-98.