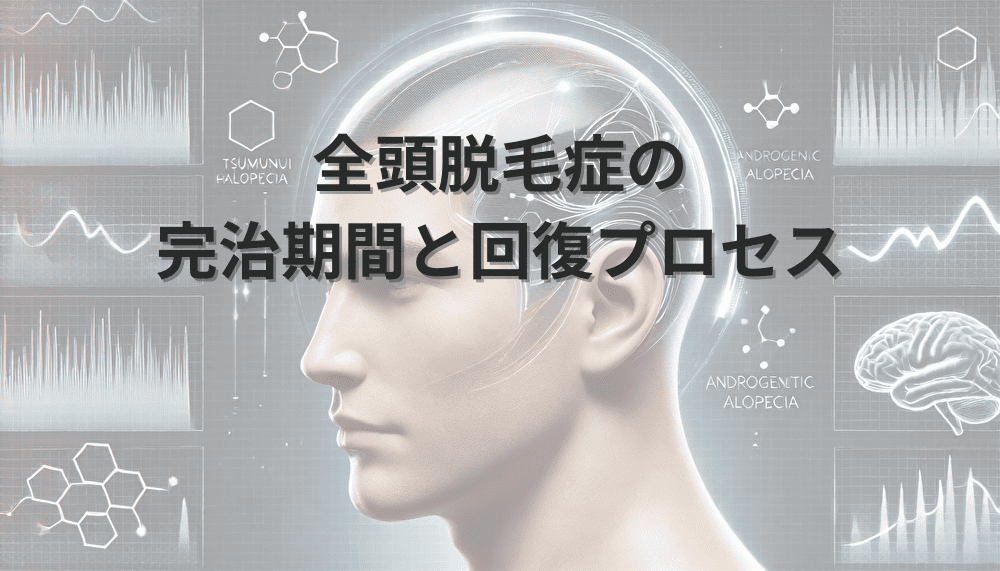

前田 祐助
AGAメディカルケアクリニック 統括院長
【経歴】
- 慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
- 慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
- 大手AGAクリニック(院長)を経て、薄毛・AGA治療の2018年AGAメディカルケアクリニック新宿院を開設
- 2020年に2院目となるAGAメディカルケアクリニック横浜院を開設
- 2023年に3院目となるAGAメディカルケアクリニック東京八重洲院を開設
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
- 3万人以上※
- ※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
全頭脱毛症は頭髪がほぼ全域にわたって脱落する状態を指し、見た目や精神的な負担が大きいといえます。
しかし一人ひとりの症状や体質に合わせて適切な治療を行うことで、発毛を期待できるケースも少なくありません。
この記事では全頭型脱毛症の原因や回復までの流れ、そしてどのように治療していくかを多角的に解説します。
全頭脱毛症とは
頭部全体の毛髪が脱落する全頭型脱毛症は、単なる部分的な抜け毛とは異なる特徴を持ちます。
髪の毛の多くが短期間で抜けてしまうため、外見的な変化だけでなく心身への負担が大きく、周囲からの理解や治療方法を慎重に検討する必要があります。
はじめに、全頭脱毛症の基礎的な概要を整理し、他の脱毛症との違いや自己免疫との関連などを確認していきましょう。
全頭脱毛症における頻度や年齢層
脱毛症はさまざまなタイプがありますが、特に頭部全体に症状が及ぶものを全頭脱毛症と呼びます。
実際のところ、その発症頻度は他の脱毛症に比べて多いわけではありません。しかし年齢や性別を問わず起こりうるため、突発的に症状が進んで悩まされる方もいます。
治療の経過や発症年齢によっても回復のスピードや再発リスクが変わります。
全頭脱毛症の症状
- 頭髪全体が比較的短期間で抜け落ちる
- 自己免疫反応が関与する可能性
- 年齢・性別を問わず発症する
- 大きな精神的ストレスにつながることがある
- 再発や長引くケースもみられる
症状の進行は個人差が大きく、短期間のうちにほとんどの髪が抜けるケースもあれば、段階的に脱毛範囲が広がっていく場合もあります。
全頭脱毛症の基礎データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原因の一例 | 免疫反応、遺伝的因子、ストレスなど |
| 発症しやすい年代 | 乳児期~高齢期まで幅広い |
| 主な症状 | 頭皮全体の脱毛、眉毛・体毛の脱落もみられる |
| 精神的影響 | 見た目の変化による不安や対人関係の悩みなど |
| 受診のきっかけ | 急激な抜け毛、頭皮トラブル、不安感など |
全頭脱毛症の特徴
全頭脱毛症の最大の特徴は、頭部の大部分または全域にわたって脱毛が進行する点です。
自己免疫のメカニズムが関わると考えられており、特に自己免疫性疾患を持つ方に併発することもあります。
眉毛やまつげ、体毛などの全身の毛が抜けるケースも見られ、外見の大きな変化が起こりやすいのが特徴です。
進行パターン
発症初期は円形脱毛症のように部分的な脱毛から始まることがありますが、その後急速に範囲が拡大し、ほとんどの髪が抜ける段階に移行する方もいます。
また、脱毛の進行速度は人によって大きく異なり、数週間から数か月で急激に髪が抜けていくケースや、ゆるやかに脱毛が続くケースなど、多様なパターンが考えられます。
自己免疫との関係
円形脱毛症を含む自己免疫性の脱毛症では、免疫システムが誤作動を起こし、自身の毛根を攻撃するとされています。全頭脱毛症の場合も同様の仕組みが関与していると考えられています。
ただし免疫が影響を与える度合いは人によって異なるため、一概に「免疫抑制だけで回復できる」とは限りません。
複数の要因が重なると髪の成長サイクルに混乱が生じ、脱毛が進行する可能性が高まります。
他の脱毛症との違い
AGA(男性型脱毛症)や産後脱毛などはホルモンや生活習慣が主な要因になりやすいですが、全頭脱毛症は自己免疫反応が強く疑われます。
また、脱毛範囲も頭頂部に限定されるケースが多いAGAとは異なり、頭部全域におよぶため精神的負担が重くなる傾向があります。
治療方針や改善に向けた取り組み方法も異なるため、早めの受診と正確な診断が大切です。
全頭脱毛症の原因
全頭型脱毛症が起こる背景には、自己免疫反応の関与だけでなく、複数の要因が組み合わさって脱毛が進行する場合も多いです。
生活習慣や遺伝、ストレスなど、人によって影響が異なるため、原因を明確にするには医療機関での検査や診察が欠かせません。
ここでは、考えられる主な原因について見ていきましょう。
全頭脱毛症の原因を考えるときのポイント
| 因子 | 内容 |
|---|---|
| 免疫反応 | 自己免疫が毛根を攻撃し、脱毛を引き起こすことがある |
| 遺伝 | 家族に脱毛症の既往があると発症リスクが上がる可能性 |
| ストレス | 精神的負担が大きいとホルモンや免疫バランスが乱れやすい |
| 栄養不良 | タンパク質やビタミン不足で毛髪の再生が滞りやすい |
| ホルモンの変動 | 性ホルモンのバランス不調が髪の成長に影響を与える |
| 加齢 | 年齢を重ねることで髪自体の成長力が低下することもある |
これらの要素が単独または複合的に作用することで、髪の成長が阻害されやすくなると考えられています。
免疫システムの異常
円形脱毛症や全頭型脱毛症は自己免疫性疾患の一つに分類されるケースが多く、免疫系が本来は異物を攻撃するべきところを誤って自分の毛根を攻撃してしまうと考えられています。
この自己免疫反応は、遺伝子の組み合わせやストレス、生活習慣などさまざまな要因によって引き起こされる可能性があります。
遺伝的要因
家族に脱毛症の既往がある場合、同じような形態の脱毛症を発症しやすいとされています。ただし、遺伝的素因があっても必ず発症するわけではありません。
遺伝と環境、免疫の働きなどが重なって初めて髪の成長サイクルが乱れ、脱毛症の症状が顕在化する方が多いです。
ストレスとの関連
ストレスは免疫機能やホルモンバランスを変化させ、脱毛リスクを高める要因になると考えられています。
仕事のプレッシャーや家族関係、あるいは金銭面の不安など、慢性的にストレスを受け続けると頭皮への血流が滞りがちになり、毛根への栄養供給が不十分になりやすいです。
日常生活での注意点
日々の生活の中で、栄養バランスのとれた食事や適度な運動、質の良い睡眠などを意識することが大切です。
特にタンパク質やミネラル、ビタミンを積極的に摂ると、髪の土台となる頭皮環境を整えやすくなります。
また、ストレス発散を図る時間を確保し、自分なりのリラックス方法を見つけることで、脱毛リスクを抑える手助けになりやすいです。
全頭脱毛症における完治までの期間の目安
脱毛症は個人差が大きいため、全頭脱毛症の完治期間も一概に「○か月」や「○年」と断定できません。
しかし過去の臨床経験や研究データを見ると、一定の期間をかけて毛髪が再生する例もあります。
ここでは、そのおおまかな回復期間の目安や、再発リスクなども含めて解説します。
全頭脱毛症の完治期間に影響する要素
- 発症時の年齢や体質
- 症状の進行度合い
- 免疫系やホルモンバランスの状態
- 治療法の組み合わせや継続状況
- ストレスのコントロール状況
これらの要素によって、全頭脱毛症の完治期間は数か月程度で改善するケースもあれば、数年単位で回復を目指すケースもあります。
全頭脱毛症の経過と期間
| ケース | おおよその期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 軽度 | 6か月~1年程度 | 円形脱毛症から移行した場合など、発毛の兆しが早期に見られる |
| 中等度 | 1年~2年程度 | 比較的広範囲にわたる脱毛だが、早期治療で回復傾向を示しやすい |
| 重度 | 2年以上かかることもある | 免疫機能の乱れが大きく、治療過程で再発を繰り返しやすい |
| 再発が多い例 | 不定 | 回復と脱毛を繰り返しながら徐々に改善を目指す |
完治期間の個人差
全頭脱毛症の完治期間は人によって大幅に変動します。発症年齢やホルモンバランス、自己免疫疾患の有無など、多くの要因が回復ペースを左右します。
特に重度の脱毛であっても、適切な治療とセルフケアの継続によって一定の発毛を期待できる場合があります。
一方、比較的軽症だと診断されても、心理的ストレスが続くと抜け毛が長引くケースもあります。
軽症から中等度の場合
脱毛範囲や頭皮の状態がまだ比較的良好である場合は、発毛が早く始まるケースが多いです。
特に育毛剤やステロイド外用薬などの薬物療法を組み合わせながら、栄養面や生活習慣を整えると、半年から1年程度で目に見えて髪が伸びてくる事例も報告されています。
ただし、治療を中断したり、ストレスが増大したりすると、再び脱毛が進むケースもあるため注意が必要です。
再発リスクと長期的な見通し
全頭型脱毛症は一度治療がうまく進んでも、免疫バランスやホルモン状態の変化によって再発する可能性があります。
発毛が始まったからといって治療をすぐにやめるのではなく、定期的な通院や頭皮ケアを継続することが重要です。
再発のたびに治療が長引く可能性も考慮し、長い期間でのヘアケア計画を立てると良いでしょう。
治療計画の重要性
全頭脱毛症の治療では、医師による診察や検査で現在の頭皮環境と全身状態を把握し、その上で効果が期待できる治療を組み合わせると良いです。
症状が軽い段階でも放置せず、早めに受診して原因を特定し、適切にケアすると回復までの期間を短縮しやすくなります。
長期的な展望を持った治療計画のもとで、定期的に頭皮の状態を評価しながら取り組みを続けていきましょう。
回復プロセスのステージ
全頭脱毛症の回復には、いくつかの段階があります。初期の炎症を鎮め、発毛を促し、その状態を維持しながら再発を防ぐ流れを理解しておくと、治療方針を考えるうえで役立ちます。
ここでは回復プロセスを大まかに区分し、それぞれの段階で何を意識するべきかを確認します。
回復の段階
段階を踏まえながら治療を進めると、発毛効果の定着をめざしやすくなります。
| 段階 | 主なケア内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 初期段階 | 抗炎症治療、免疫抑制療法など | 毛根部の炎症を抑えて抜け毛の進行を抑える |
| 中期段階 | 育毛剤や栄養補給、頭皮の保湿 | 新たに生えてくる髪を促進し頭皮環境を整える |
| 後期段階 | スカルプケア、生活習慣の改善 | 生えてきた髪を定着させ、健康な毛髪サイクルへ導く |
| 再発防止 | 定期的な通院やメンタルケア | 免疫バランスを維持し、脱毛の繰り返しを抑える |
初期段階:炎症の抑制
全頭脱毛症の初期段階では、頭皮の炎症を制御するのが中心となります。ステロイド外用薬や免疫抑制剤などを医師の判断で使用し、毛根がダメージを受け続けないようにします。
この段階で適切な対処を行うと、進行を抑えて回復の基盤を作りやすくなります。
中期段階:発毛促進
炎症がある程度落ち着いたら、毛母細胞の活動を高めるために育毛剤や栄養補助などを組み合わせる段階に入ります。
ビタミンやミネラル、タンパク質など髪に良い栄養素を意識した食事の見直しも重要です。
適度な頭皮マッサージやシャンプー選びなど、日常的なケアが大きな役割を果たします。
後期段階:頭皮環境の維持
発毛が確認された後は、頭皮の環境を整えて新しく生えた髪をしっかり育てることに注力します。
日々のシャンプーやトリートメント、紫外線対策などを続けながら、頭皮の乾燥や血行不良を防ぎます。
定期的な医師のチェックも受けると、再発リスクを管理しながら健康な毛髪を維持しやすくなります。
再発防止のための取り組み
再発を防ぐためには、再び自己免疫が活性化しないよう、定期的な検査やメンタルケアが大切です。
生活習慣の乱れやストレスが引き金になる場合もあるので、睡眠の確保やストレス発散を意識して行動すると良いでしょう。
再発の兆候が出た場合は早めに受診し、炎症の拡大を抑えるのが回復への近道です。
治療方法とクリニックでの取り組み
全頭型脱毛症の治療には多角的な方法があります。薬物療法や免疫療法、注射などを組み合わせて行う場合が多く、クリニックでのサポートも重要です。
ここでは、一般的に行われる治療方法と、クリニックがどのようにサポートしていくかを説明します。
複数の治療法を併用するメリット
- 免疫抑制効果と発毛促進効果を同時に期待できる
- 患者の症状に合わせた柔軟な治療計画が立てやすい
- 生活習慣やメンタル面への指導を受けやすい
- 定期的な評価で治療方法を修正できる
- 安心して治療を続けやすい
ただ単に薬を使うだけでなく、頭皮や全身の健康状態に注目しながら継続的にケアを受けることが大切です。
全頭脱毛症の治療方法
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 外用薬 | ステロイド外用、育毛剤などを頭皮に塗布 |
| 内服薬 | 抗免疫薬やホルモン調整剤などを服用 |
| 局所免疫療法 | 頭皮に化学的な刺激を与えて発毛を促す方法 |
| 注射・点滴療法 | 炎症や免疫反応のコントロールのための薬剤を直接投与 |
| メンタルケア | 心理的ストレスへのアプローチ、カウンセリングなど |
| 生活習慣の改善指導 | 栄養指導、睡眠指導、運動指導などで身体全体の健康を底上げ |
薬物療法
ステロイド外用薬や免疫抑制剤の内服などが代表的です。特に頭皮の炎症が強い場合は、外用薬と内服薬を組み合わせるときがあります。
ただし副作用もあるため、医師の指示のもとで用法用量を守りながら使用する必要があります。体質や症状に合った薬剤を選び、効果を確認しながら治療を進めます。
免疫療法
局所免疫療法など、意図的に炎症反応を起こすことで免疫の誤作動をリセットし、発毛を促す方法が用いられる場合があります。
これには専門的な設備と経験が必要で、効果が出るまで時間を要する方もいます。定期的な通院と医師の観察を踏まえて、適切なタイミングで治療方法を調整していきます。
注射・点滴療法
ステロイドやビタミン、その他の栄養成分を点滴や注射で直接体内に届ける方法も選択肢に含まれます。
免疫抑制効果や頭皮環境の改善を狙って行い、全頭脱毛症の進行を抑えたり、発毛を後押ししたりすることが期待されます。
施術後の経過観察を行いながら、必要に応じて他の治療とも併用していきます。
クリニックでのサポート
クリニックでは、治療自体だけでなくメンタル面でのサポートや生活習慣指導も行います。
脱毛が進行している最中は精神的負担が大きいため、スタッフや専門医とのコミュニケーションが回復力を高めるうえで大切です。
定期的に頭皮の状態をチェックし、必要であれば治療プランの見直しや追加の検査を行うと、より効果的に髪の回復を目指しやすくなります。
日常でできるケアと予防
全頭脱毛症の治療は医療機関で行うものだけではありません。日常生活の中で頭皮や髪をいたわる習慣を身につけると、再発予防にもつながります。
ここでは、誰でも取り入れやすいセルフケアのポイントを紹介します。
日常ケアで意識したいこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 頭皮ケア | 刺激の少ないシャンプー、適度な洗髪頻度、頭皮マッサージ |
| 栄養バランス | タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取 |
| ストレス管理 | 適度な運動、趣味の時間、カウンセリングなど |
| 生活リズム | 質の良い睡眠、規則正しい食事、アルコールや喫煙を控える |
| 紫外線対策 | 帽子や日傘などで直射日光から頭皮を守る |
日常ケアのポイント
- シャンプーを低刺激のものに変えて洗髪時間を短縮する
- ドライヤーの温度を高温にしすぎず、頭皮を熱から保護する
- 食生活を見直し、タンパク質と野菜の摂取を増やす
- 軽い運動や趣味でストレスを発散しやすくする
- 頭皮の乾燥や炎症を防ぐため、保湿ローションを使用する
こうしたセルフケアを継続することで、頭皮環境が整いやすくなり、治療効果の向上や再発リスクの低減を目指せます。
頭皮ケア
髪と同様、頭皮を健康に保つことが重要です。洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮を傷める可能性があるため、自分の肌質に合ったものを選びましょう。
指の腹を使って優しくマッサージするように洗うと、血行を促進できるだけでなくリラックス効果も期待できます。
栄養バランスの見直し
髪はタンパク質を主成分としています。十分なタンパク質を摂取し、あわせてビタミンやミネラルを補給する心がけが大切です。
特に亜鉛や鉄分が不足すると脱毛が進みやすくなるため、肉や魚、豆類、野菜などをバランスよく取り入れましょう。サプリメントを活用する場合は、医師や栄養士に相談すると安心です。
ストレスケア
ストレスは全頭脱毛症を含むさまざまな疾患の悪化要因になり得ます。忙しい日常の中でも、自分がリラックスできる時間を確保し、趣味や運動などで上手に気分転換を図ると良いでしょう。
また、どうしても不安が大きいときは、医療機関や専門カウンセラーに相談すると精神面のサポートを得やすくなります。
生活リズムの改善
睡眠不足や過度の飲酒、喫煙はホルモンバランスや血流に影響を及ぼし、髪の成長サイクルを乱します。
規則正しい生活リズムを維持し、できるだけ夜更かしを避けるのも頭皮環境を整えるうえで大切です。可能であれば軽い運動を習慣化し、睡眠の質を上げると身体の基礎代謝や免疫機能にも好影響を与えます。
全頭脱毛症とAGA治療の関係
全頭型脱毛症とAGA(男性型脱毛症)は原因や症状のパターンが異なりますが、クリニックではどちらも毛髪や頭皮に関する治療を行うため、共通点もあります。
特に男性であれば全頭脱毛症が回復した後にAGAの治療を検討するケースや、AGAと併発するケースが存在します。
全頭脱毛症とAGAの比較
| 項目 | 全頭型脱毛症 | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 自己免疫反応、遺伝、ストレス | 男性ホルモン(DHT)の作用、遺伝 |
| 脱毛部位 | 頭部全域 | 前頭部~頭頂部中心 |
| 治療アプローチ | 免疫抑制、発毛促進 | ホルモン抑制薬、育毛剤など |
| 再発の可能性 | あり | 進行性だが適切な治療で抑えられる場合あり |
| 性別 | 男女問わず発症 | 主に男性に多い(女性型も存在) |
全頭脱毛症とAGA治療を考えるポイント
- 両者を併発するケースもあり、同時に治療を検討する必要がある
- 全頭脱毛症が回復したのちにAGAが顕在化する可能性もある
- クリニックで頭皮や毛根の状態を正確に把握しながら治療する
- 免疫とホルモン、両方の視点から取り組みが必要になる場合がある
AGAとの共通点
どちらも脱毛が進行するという点で共通しています。毛髪を再生させるには毛根の健康が鍵を握るため、血流促進や栄養補給といった基礎的なケアは同様に大切です。
また、ストレスが引き金となって症状が悪化する点も類似しています。
併発の可能性
自己免疫反応による全頭型脱毛症と、ホルモン作用によるAGAは原因が異なりますが、同時に発症する例もないわけではありません。
特に男性で、家族にAGAの既往がある場合は、もともとAGAのリスクが高いところへ免疫系のトラブルが加わると脱毛症状が複雑化するケースがあります。
将来の薄毛対策
全頭脱毛症が回復したとしても、家族性のAGAが進行する可能性や加齢による薄毛リスクが存在します。
早めに毛髪や頭皮のケアに取り組み、定期的に頭皮チェックを行うと、薄毛の進行を抑えられます。何らかの変化を感じたら、早期にクリニックで相談しておくと安心です。
クリニックへの相談が大切
専門家に相談することで、全頭脱毛症とAGAを的確に区別し、治療の優先順位や方針を立てやすくなります。
自分で判断せず、医師や専門スタッフに状態を見てもらいながら治療を進めるとリスクの把握や合併症の予防もしやすくなるでしょう。
全頭脱毛症を経験した方のQOLと再発予防
全頭脱毛症は外見上の変化が大きいため、仕事や学校、家庭での生活にも影響が及ぶ場合があります。
しかし適切に治療を続け、再発を防ぎながら自身のQOL(生活の質)を保つことは十分に可能です。
ここでは、社会生活への影響や周囲のサポート、定期的なフォローアップの必要性などに注目し、再発予防についても確認します。
全頭脱毛症の経験者が気をつけたい点
- ウィッグや帽子で頭皮を保護する
- 周囲の理解を得るために医師の説明資料を活用する
- 定期的に通院し、微細な変化にも早く対応する
- ストレスを抱え込みすぎない環境づくり
- 衛生的で快適な頭皮環境を維持する
こうした点を意識しながら生活を送ると、脱毛症の進行を抑えつつ日常を楽しみやすくなります。
全頭脱毛症の再発予防とQOL向上
| 取り組み | 具体的な内容 |
|---|---|
| ウィッグ・帽子の活用 | 自分に合ったウィッグや帽子を選んで外出や仕事をスムーズに進める |
| カウンセリング | 心理的負担を軽減し、ストレスコントロールを学ぶ |
| 生活習慣の調整 | 食生活、睡眠、運動を見直し、免疫バランスを整える |
| 定期検診 | 再発の兆候を早めにキャッチし、適切な治療に移行できるようにする |
| サポートを得る | 家族や友人、同じ経験を持つ仲間との情報共有で心の支えを得る |
社会生活への影響
髪の悩みは個人のセルフイメージに直結しやすく、外出時や職場での人間関係など、さまざまな場面で自己肯定感に影響を及ぼします。
ウィッグや帽子を使用しているのを周囲に打ち明けにくかったり、学校や職場でからかいの対象になってしまったりすることも考えられます。
このような状況に対処するためには、医師やカウンセラーの助言を得ながら、必要に応じて周囲に正しい情報を伝えると良いです。
周囲の理解とサポート
全頭脱毛症に対する正しい理解が広まると、本人が必要以上に気負わずに日常生活を送れます。家族や友人、職場の同僚など身近な人々には、可能な範囲で現状を共有し、協力を得ると良いでしょう。
学校や企業では、カウンセリング制度を活用したり、通院のための配慮をお願いしたりすると、安心して治療と仕事・学業を両立しやすくなります。
定期的なフォローアップ
全頭脱毛症は再発の可能性があり、症状が落ち着いているように見えても内在的に免疫バランスが乱れている場合もあります。
定期的に通院し、頭皮や発毛状況をチェックすると、早期に異変に気付き適切な処置を検討できます。治療期間が長期に及ぶケースも多いため、担当医とのコミュニケーションを継続していく姿勢が求められます。
心理的ケアの重要性
脱毛症に対する悩みは外見だけにとどまりません。うつ状態や対人恐怖など、心理面での問題が生じることも珍しくありません。
心のケアを怠ると、ストレスが増して免疫状態がさらに乱れる可能性があります。
必要に応じて専門のカウンセラーを利用するほか、脱毛症の患者同士が情報交換できるコミュニティに参加してみると、新たな視点や安心感を得られるでしょう。
参考文献
FUKUYAMA, Masahiro, et al. Elucidation of demographic, clinical and trichoscopic features for early diagnosis of self‐healing acute diffuse and total alopecia. The Journal of Dermatology, 2020, 47.6: 583-591.
LEW, Bark-Lynn; SHIN, Min-Kyung; SIM, Woo-Young. Acute diffuse and total alopecia: A new subtype of alopecia areata with a favorable prognosis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2009, 60.1: 85-93.
JABBARI, A., et al. An open-label pilot study to evaluate the efficacy of tofacitinib in moderate to severe patch-type alopecia areata, totalis, and universalis. Journal of Investigative Dermatology, 2018, 138.7: 1539-1545.
TRÜEB, Ralph M.; DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni. Alopecia areata: a comprehensive review of pathogenesis and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2018, 54: 68-87.
WHITING, David A. Histopathologic features of alopecia areata: a new look. Archives of dermatology, 2003, 139.12: 1555-1559.
SANTOS, Zenildo; AVCI, Pinar; HAMBLIN, Michael R. Drug discovery for alopecia: gone today, hair tomorrow. Expert opinion on drug discovery, 2015, 10.3: 269-292.
TOSTI, Antonella; DUQUE-ESTRADA, Bruna. Treatment strategies for alopecia. Expert opinion on pharmacotherapy, 2009, 10.6: 1017-1026.
FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.
