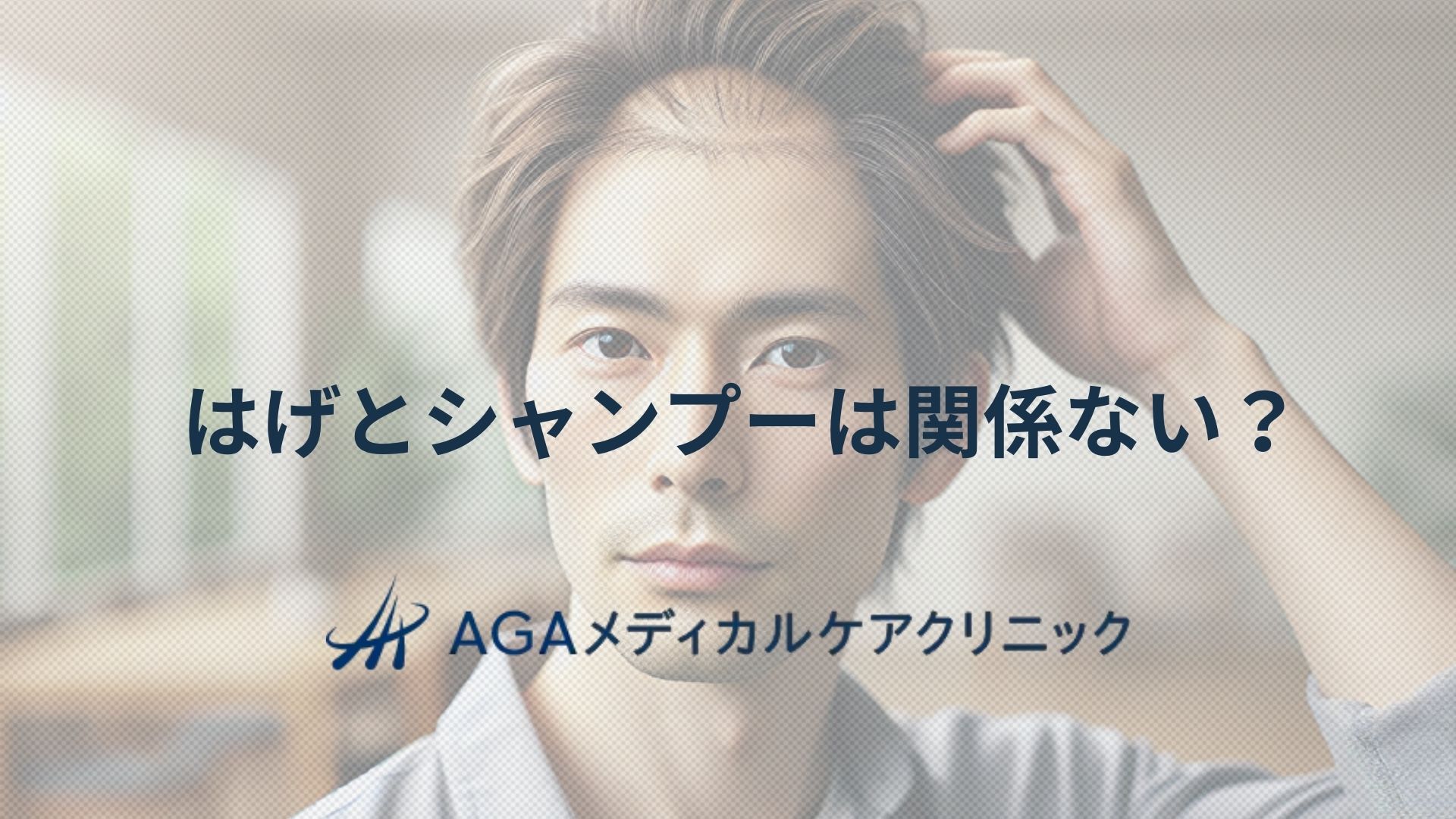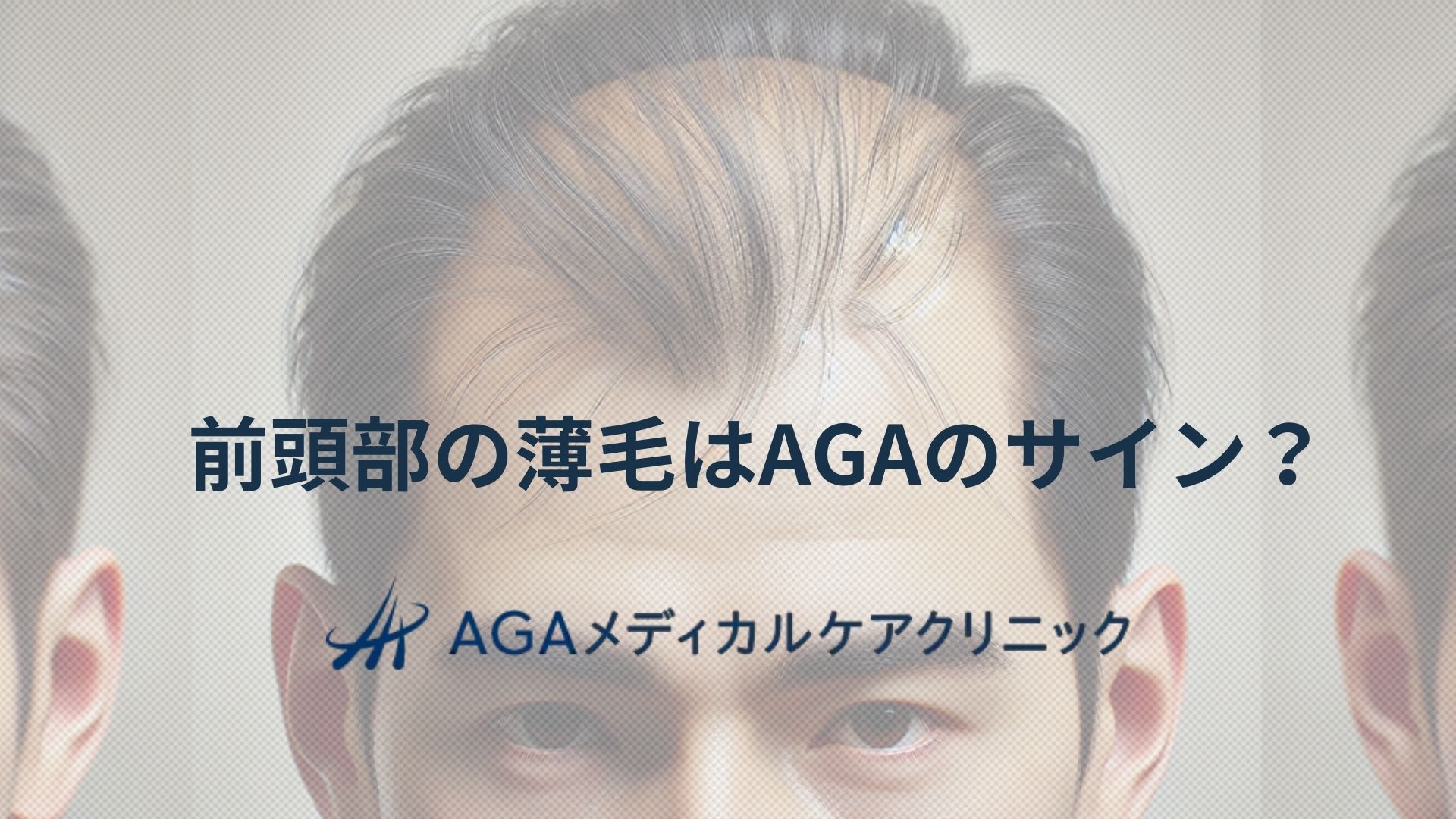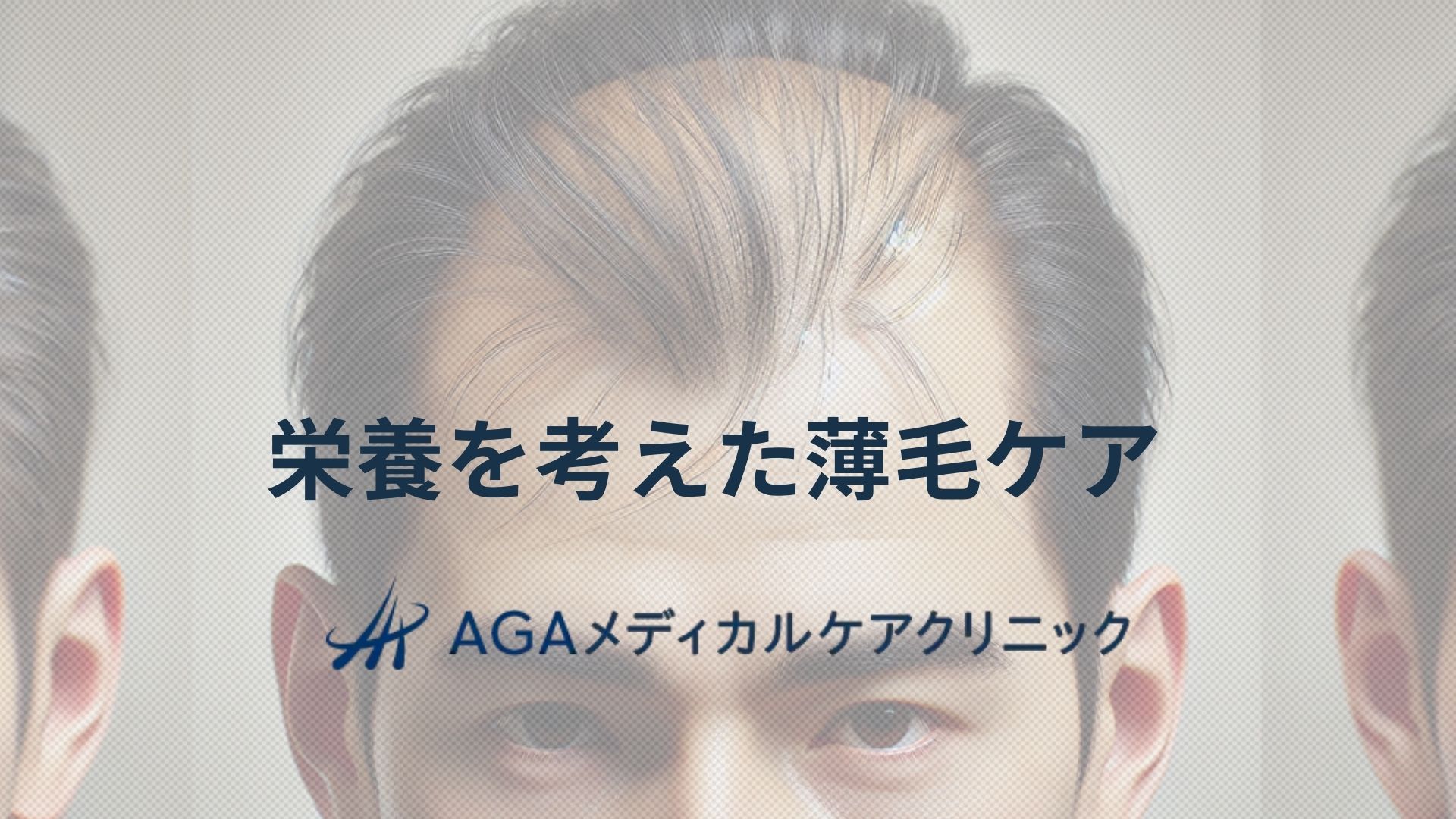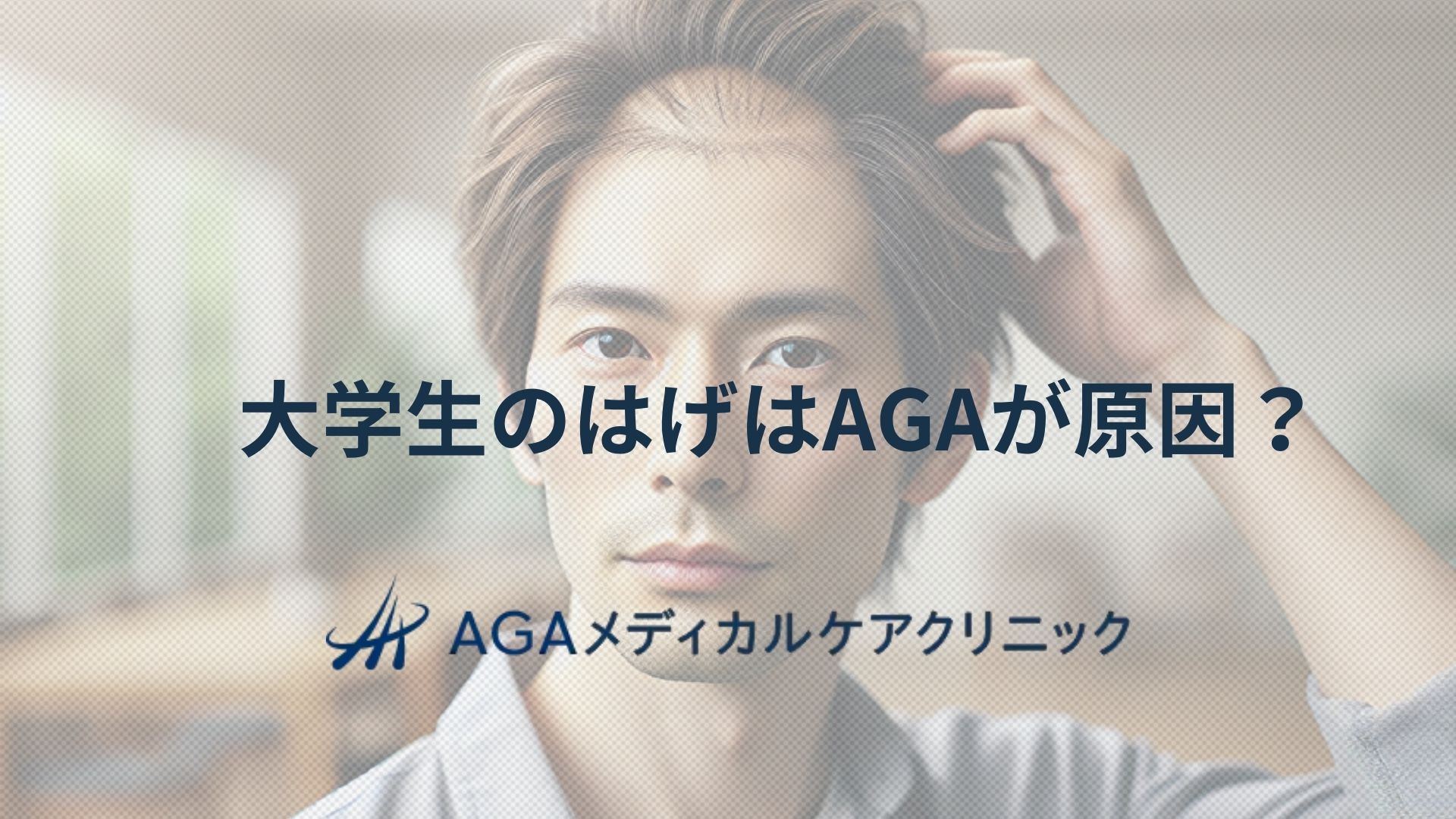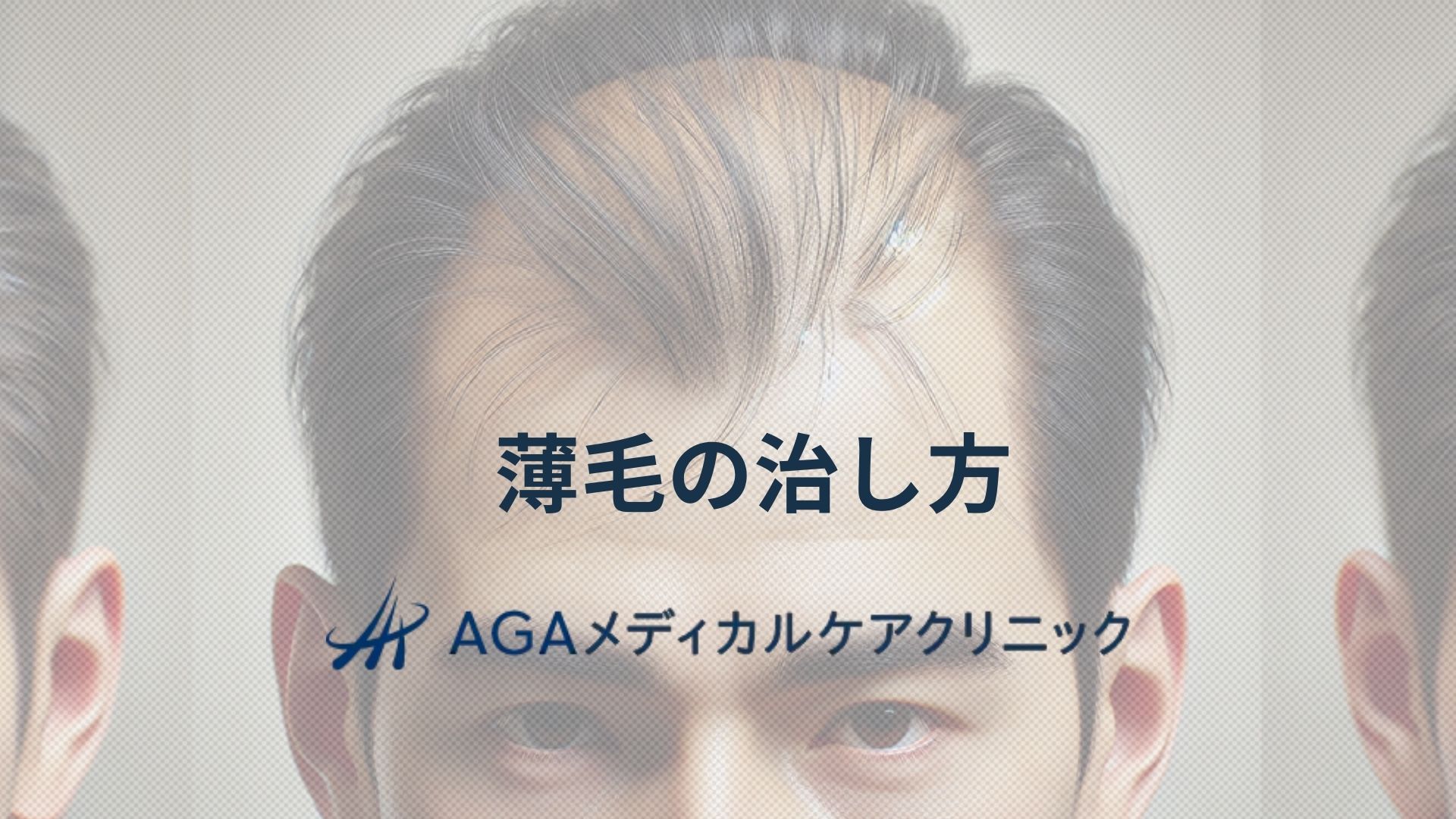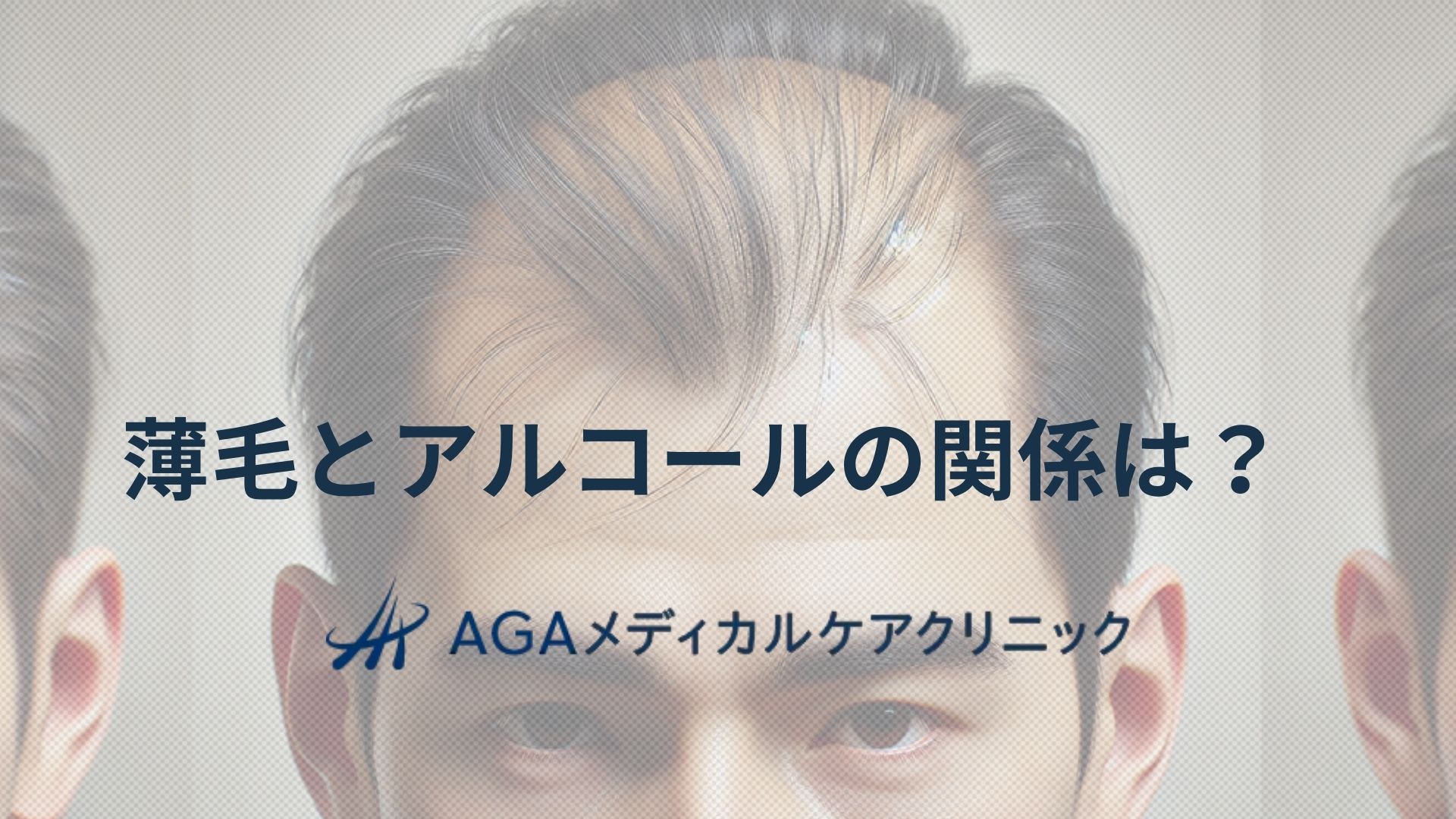

前田 祐助
AGAメディカルケアクリニック 統括院長
【経歴】
- 慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
- 慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
- 大手AGAクリニック(院長)を経て、薄毛・AGA治療の2018年AGAメディカルケアクリニック新宿院を開設
- 2020年に2院目となるAGAメディカルケアクリニック横浜院を開設
- 2023年に3院目となるAGAメディカルケアクリニック東京八重洲院を開設
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
- 3万人以上※
- ※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
日常的にお酒を飲むと髪に悪影響が及ぶという話を耳にする人は多いかもしれません。
アルコールと薄毛の関係は医学的にまったくの無関係ではありませんが、どの程度の飲酒量や頻度が抜け毛の進行を早める原因になるのか気になる方もいるでしょう。
体内でアルコールが分解される過程では肝臓に大きな負担がかかり、頭皮や毛髪の健康を保つために必要な栄養素が不足しやすくなる可能性があります。
また、飲みすぎによる睡眠不足やホルモンバランスの変化が髪の成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。
この記事ではアルコールと薄毛の関係を多角的に解説して飲酒習慣とAGA治療の両立を考えるうえで役立つ情報を紹介します。
なぜアルコールが薄毛と関係するといわれるのか
栄養豊富なお酒なら髪の毛にも良いのではという見方をする人もいますが、抜け毛が多い人やAGAのリスクがある方にとって飲酒は軽視できません。
日頃からお酒を飲むときに頭皮や髪にどのような作用が生じるのかを知っておくと自分に合った対策を考える際に役立ちます。
原因物質アセトアルデヒドへの注目
アルコールを体内に摂取すると肝臓で分解が始まります。肝臓はアルコールをアセトアルデヒドに変換し、それをさらに酢酸へと変換して最終的に体外へ排出します。
アセトアルデヒドは有害物質であり、頭痛や吐き気などを引き起こす原因です。
肝機能が低下している人はこの物質をうまく分解できず、結果的に体内に残るアセトアルデヒドが頭皮の健康を損ねる要因になりえます。
肝臓が正常に働かないと髪の毛の成長にも悪影響が及ぶので注意が必要です。
栄養不足と抜け毛の関連
アルコールの摂りすぎは栄養面にも悪影響があります。
肝臓がアルコールを分解するためにアミノ酸やビタミン、ミネラルなどの栄養素を多く使ってしまう場合があり、その分だけ毛髪に行き渡る栄養が減る可能性があります。
髪の毛はタンパク質で構成されているため、タンパク質をつくるアミノ酸不足や血行不良で起こる栄養不足が薄毛や抜け毛の要因につながることがあります。
髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 髪への主な役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 毛髪の主成分となるケラチン合成を助ける | 肉、魚、大豆製品など |
| ビタミンB群 | 新陳代謝を助け、頭皮環境を整える | レバー、卵、緑黄色野菜など |
| 亜鉛 | タンパク質合成をサポート | 牡蠣、牛肉、ナッツ類など |
| 鉄分 | 酸素を頭皮や髪に届ける | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
栄養素が不足すると髪の成長サイクルが乱れやすくなり、抜け毛が増えるリスクが高まると考えられます。
ホルモンバランスと発毛への影響
男性型脱毛症(AGA)はジヒドロテストステロンというホルモンが深く関係します。
飲酒によって男性ホルモンの分泌が増えると薄毛を進行させる原因物質が増加する可能性があります。
女性も過度なアルコール摂取でホルモンバランスが乱れ、女性ホルモンが低下すると髪のツヤやボリュームが失われることがあります。
頭皮環境に及ぼすリスク
お酒を飲むと身体が脱水状態に陥りやすくなり、頭皮の皮脂バランスが崩れることがあります。
飲み会の後に頭皮がベタつきやすい、あるいは乾燥しやすいと感じる人は多いかもしれません。
皮脂過剰や乾燥は頭皮のトラブルを引き起こして薄毛の原因となる可能性があります。
飲酒習慣が髪の成長に与える影響
アルコールを飲むことで起こりうる体内の変化はさまざまです。頭皮や髪の毛に直接ダメージを与えるわけではない場合でも、間接的に悪影響を及ぼすケースがあります。
特に毎日のように飲む人はAGA治療や薄毛予防を考えるうえで飲酒の影響を理解しておくことが重要です。
肝臓への負担が増えると髪に悪影響を及ぼす?
肝臓は体内の解毒機能を担う重要な臓器です。日常的にアルコールを飲むと肝機能が低下し、解毒がうまく進まない状態になる可能性があります。
肝臓の働きが低下すると血液中の老廃物が増えって頭皮に良くない物質が蓄積しやすくなります。
また、肝機能が低下すれば体内のタンパク質合成能力も下がり、髪の成長に必要な栄養素の供給が十分に行われにくくなるかもしれません。
肝機能低下が髪にもたらす結果
| 症状や状態 | 主な原因 | 髪や頭皮への影響 |
|---|---|---|
| 老廃物の増加 | アセトアルデヒドの分解が遅れるなど | 頭皮の炎症や血行不良 |
| タンパク質不足 | 肝機能低下で合成効率が落ちる | 毛髪のハリ・コシの低下 |
| ホルモン代謝乱れ | ホルモンの分解や調整が遅れる | AGAの進行を早める要因に |
睡眠の質が低下し成長ホルモンが減少する?
睡眠時に分泌される成長ホルモンは髪の毛の発育を支えています。
過度な飲酒で就寝すると睡眠の質が下がり、深い眠りに入る時間が短くなります。
深い眠りの間に成長ホルモンが分泌されやすいことから、飲酒による睡眠不足や睡眠の質の低下は抜け毛の進行リスクを高めると考えられます。
十分に休めていない頭皮環境では髪の毛の成長が滞り、発毛サイクルも乱れやすくなるでしょう。
睡眠不足が招く頭皮や髪の変化
| 変化 | 原因 | 影響 |
|---|---|---|
| 成長ホルモンの減少 | 深い睡眠の不足 | 抜け毛が増える場合がある |
| ストレス増加 | 質の高い休息が得られない | ホルモンバランスの乱れ |
| 血行不良 | 自律神経の乱れ | 栄養が髪まで届きにくくなる |
お酒と同時に摂りがちな食事の落とし穴
お酒を飲む際に揚げ物や塩分の高いおつまみをたくさん食べる人は多いです。
これらの食品は糖質や脂質、塩分を過度に含む場合があり、体重増加や血圧の上昇だけでなく頭皮環境にも悪影響を与える恐れがあります。
特に塩分の過剰摂取は血行を阻害して髪の毛の発育を損なう要因になるかもしれません。
おすすめの食事選びのヒント
- 肝臓に負担がかかりにくい食材を選ぶ
- 野菜や海藻類などミネラル豊富な副菜を追加する
- タンパク質を良いバランスで摂る
- 飲む量を減らす工夫としてノンアルコールドリンクを利用する
女性の薄毛に与える影響
女性の体は男性よりもアルコール分解能力が低いといわれることがあります。肝臓に負担をかけやすい状況では女性ホルモンの分泌も乱れやすくなります。
女性ホルモンが減少すると髪のコシやハリが失われるだけでなく、抜け毛が進行する可能性があります。
飲酒習慣を見直すだけで女性の薄毛悩みが改善に向かう例もあるため自分の適量を見極めることが大切です。
薄毛とアルコールのかかわりを検証するデータ紹介
医療や栄養学の分野ではアルコールの過度な摂取が健康に大きなリスクを及ぼすという情報が数多くあります。
薄毛やAGAとの直接的な因果関係を示す研究は限定的ですが、間接的に関連があると考えられるデータは確認されています。
肝機能と薄毛の関係を調べた研究
専門家が行った研究によると肝機能が低下した人は頭髪に栄養が行き届きにくく、抜け毛が増える傾向があると報告されています。
医学的に肝臓が果たす役割は多岐にわたり、毛髪だけでなく全身の健康を守るためにも肝機能を損なう過度の飲酒は避けるほうが良いという声が多いです。
肝機能低下とAGA発症リスクの比較
| 項目 | 肝機能が正常な群 | 肝機能が低下した群 |
|---|---|---|
| AGA発症率 | 10%未満 | 15%近く |
| 抜け毛が進行した割合 | 約12% | 約18% |
| 自覚症状の強さ | やや少ない傾向 | やや強い傾向 |
調査人数や対象者の生活習慣などで結果に個人差がありますが、肝機能が低下すると髪の状態にも悪い影響を及ぼしやすい可能性が示唆されています。
過剰な飲酒とAGAの関連性
AGAは遺伝やホルモンの影響が大きいといわれていますが、日常生活のなかで過剰な飲酒が引き金になると考える専門家もいます。
アセトアルデヒドの蓄積やホルモンバランスの乱れがAGA進行を早める可能性があるからです。
一方で適度な量のアルコールでは発症を直接的に引き起こすわけではないとの報告もあります。
適度な量なら血行を促進できる?
お酒には血管を拡張させる作用があるため、適量の範囲であれば血行不良の改善につながる場合もあります。
飲みすぎないことを意識すればリラックス効果やストレス解消などポジティブな側面も期待できます。
しかし、血行促進以上に肝臓への負担や睡眠の質の低下がデメリットとして大きい人もいるため、自分の体質を考慮した上で飲む量を決めることが大切です。
飲む頻度を下げれば改善が望める?
毎日大量にアルコールを摂取している場合、週に1~2回でも控えると体調面で変化を感じる人がいます。
頭髪や頭皮環境に対する改善も同様で、飲む回数を減らすだけで髪の調子が良くなったと感じる例は少なくありません。
飲酒頻度を下げることで得られた主なメリット
| 変化 | 感じた人の割合 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 朝の疲れが残りにくくなった | 約60% | 質の高い睡眠が得られ、目覚めが良くなった |
| 抜け毛が減ったと感じた | 約35% | ストレス軽減や栄養状態の改善による可能性 |
| 体重や血圧の変化が良い方向に進んだ | 約40% | カロリーや塩分を控えられ、健康状態も向上 |
数値は一部の調査を参考にした概算であり、人によって結果は異なります。
AGAを発症している場合は飲酒頻度を下げるだけで完全に抜け毛が止まるわけではありませんが、悪化を防ぐという点で一定の効果が見込める可能性があります。
適切な飲酒量と髪を守るためのポイント
飲酒が薄毛の直接原因とは断定できませんが、血行不良や栄養不足、ホルモンバランスの乱れを引き起こす要因になりやすいため注意が必要です。
飲むのをやめることが難しい方でも少し意識するだけで髪や頭皮の悪影響を軽減できるケースがあります。
適度な量とはどの程度か
一般的に健康の観点で示される目安として、1日あたり純アルコール量20g程度が適量だといわれる場合があります。
具体的にはビールなら中瓶1本程度、日本酒なら1合程度を指すことが多いです。ただし体重や性別、体質により許容度は変わります。
純アルコール量20gの目安
| 種類 | 量 | 純アルコール量の例 |
|---|---|---|
| ビール | 中瓶1本 | 約20g |
| 日本酒 | 1合(180ml) | 約22g |
| 焼酎(25度) | 100ml | 約20g |
| ワイン(12度) | 約200ml | 約19g |
この量を毎日飲むよりも、週に2日ほどは休肝日を設定して体をいたわると肝臓に過度の負担がかからず、髪の健康にとっても良い方向につながりやすいです。
飲酒時の食事選びの工夫
飲むときに何を食べるかも大切です。脂質や糖質が多い食事は頭皮環境を乱す要因となる可能性があります。
血液ドロドロ状態を避けるためには塩分や糖質を控えめにし、ビタミンやミネラルをバランスよく含む食材を取り入れることがポイントです。
飲みながら取り入れたい食品の例
| 食品カテゴリ | おすすめの食材 | 理由 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 鶏ささみ、豆腐、魚、卵 | 良質なアミノ酸を補給しやすい |
| 野菜 | ブロッコリー、ほうれん草 | ビタミンやミネラルが豊富で血行を整えやすい |
| 海藻類 | わかめ、ひじき、もずく | ミネラルや食物繊維が豊富 |
| 果物 | みかん、キウイ、ベリー類 | ビタミンCや抗酸化成分が多く美容にも良い |
こうした食材を取り入れると髪の毛や頭皮の健康面でメリットが期待できます。
休肝日の大切さ
毎日飲むと肝臓は常にアルコール分解を優先することになり、髪の毛に必要なタンパク質やビタミンの供給が後回しになることがあります。
週に1~2日程度でも休肝日を設けると肝臓が回復する時間を確保できるため、栄養が行き届きやすくなる可能性があります。
休肝日をうまく取り入れる方法
- 週末のどちらかを完全にアルコールなしにする
- 外食や飲み会の回数を調整して事前に予定を組む
- ノンアルコールのドリンクを活用して気を紛らわせる
- 一人飲みを減らし、適度に楽しむ場面を限定する
ストレスケアと運動の取り入れ方
飲酒によってストレスを解消したいと考える人もいますが、アルコールでは根本的な解決にならない場合があります。
むしろ過度の飲酒が新たなストレスを生む可能性もあるため、運動や趣味など別の手段でストレスを発散すると心身の健康が保ちやすくなります。
ストレス軽減に役立つ習慣の例
| 方法 | 具体例 | 髪への好影響 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギングなど | 血行促進 |
| 趣味の時間 | 音楽鑑賞、読書、DIYなど | 心身のリラックス |
| マインドフルネス | 瞑想や深呼吸など | 自律神経の安定 |
| 質の高い睡眠 | 就寝前のデジタル機器オフなど | 成長ホルモンの正常分泌 |
薄毛予防とAGA治療の重要性
アルコールを控えたからといって、すべての抜け毛が自然に改善するわけではありません。
すでに男性型脱毛症(AGA)が進行している場合や、FAGA(女性の薄毛)を発症している場合は専門的な治療が必要です。
飲酒量を減らすことは頭皮環境を整える一助になりえますが、原因がホルモンや遺伝にある場合は医療的なアプローチも考えたほうが良いでしょう。
飲酒を控えても抜け毛が止まらないとき
栄養に気を配り、睡眠の質を上げても抜け毛が続く場合はAGAや他の脱毛症が進んでいる可能性があります。
この段階で自己判断だけに頼るのは危険です。専門のクリニックで毛髪診断を受けることで抜け毛の原因を明確にし、適切な治療方法を選ぶ助けになります。
AGAの治療薬とアルコールの併用リスク
AGA治療薬のなかには血圧や肝機能に影響するものがあります。
お酒と同時に飲むことで効果が減少する、あるいは副作用が出やすくなるリスクがゼロではありません。
主治医や薬剤師と相談して飲酒する場合の注意点を確認しておくことが大切です。
AGA治療薬と飲酒のリスク例
| 治療薬の種類 | 考えられるリスク | 医師に相談すべき内容 |
|---|---|---|
| フィナステリド系 | 肝機能に負担がかかる可能性 | 肝臓の状態を定期的にチェック |
| ミノキシジル系 | 血圧低下や動悸が起こる可能性 | 飲酒習慣がある場合の併用注意点 |
| その他の薬 | 成分による相互作用 | 飲む量やタイミングをどこまで制限するかなど |
医師への相談で得られるメリット
自己流で対策を進めても効果が見られない人は医療機関の受診を考えたほうが良いです。
専門の医師は頭皮や毛髪の状態を診察して治療薬や注入治療、生活習慣の改善指導などを提案できます。
飲酒習慣がある人に対しても肝臓を傷めずに治療を続けるためのアドバイスを行います。
クリニック受診の流れと費用
AGAクリニックなどでは初回カウンセリングが無料のところもあります。
医師に頭皮を診てもらい、血液検査などを行ったうえで治療内容を決める場合が多いです。
費用は治療薬の種類や治療期間により異なりますが、早期に治療を始めるほど安価に済む傾向があります。
予約を取る際には飲酒の頻度や量も伝えると診断がスムーズです。
クリニック受診時に確認すると良い内容
- 自分の抜け毛や頭皮の状態
- 飲酒量や期間、頻度
- 過去の病歴や服用中の薬
- 治療方針と費用、おおよその期間
よくある質問
飲酒をまったくやめられない場合はどうすればいいのか
まったくやめることが難しい場合でも、まずは飲む量や頻度を減らすことを検討すると良いです。
休肝日を設ける、ノンアルコールドリンクを利用するなどの方法があります。
栄養バランスを意識して肝臓や頭皮への負担を軽減する工夫を取り入れるだけでも髪の状態が改善する可能性があります。
毎日飲む人は薄毛になりやすいのか
毎日少量であれば必ずしも薄毛になるわけではありませんが、過度に飲む習慣がある人はAGAや抜け毛が進みやすいリスクが高いと考える医師は多いです。
個人差があるため一概にはいえませんが、自分の適量を超える飲酒はホルモンバランスの乱れや睡眠の質の低下を招くことが多く、注意が必要です。
ビールよりも焼酎やワインのほうが髪に良いのか
ビール、焼酎、ワインなどアルコールの種類よりも摂取量や飲む頻度のほうが大切です。
体質によっては糖質が多いお酒を控える、アルコール度数が高い種類を少量飲むなどの工夫で負担を軽減できる可能性があります。
結局は肝臓にかかる負担が問題となるため、どのお酒でも適量を守ることが最も重要です。
女性はアルコールで薄毛が進みやすいのか
女性の場合は男性よりも分解能力が低いケースが多く、肝機能が弱いと抜け毛が進行しやすくなる可能性があります。
さらに女性ホルモンが乱れることで髪のツヤやコシが失われて抜け毛が増えることがあります。
女性で薄毛が気になる場合は早めにクリニックで相談するのがおすすめです。
まとめ
アルコールをたしなむ程度なら血行促進やリラックス効果が期待できる一方、過度な飲酒は肝臓への負担やホルモンバランスの乱れ、栄養不足などを引き起こして薄毛や抜け毛の進行を促す可能性があります。
毎日のお酒が欠かせない人も休肝日を設けたり飲む量や頻度を見直したりするだけで髪や頭皮の状態が改善に向かう例があります。
すでにAGAやFAGAが疑われる場合は専門のクリニックに相談し、医師の指導のもとで治療を継続することが大切です。
アルコールと上手に付き合いながら髪の健康を守るには自分の体質を知り、適量を守る意識が重要といえます。
以上
参考文献
KOYAMA, Taro, et al. Eleven pairs of Japanese male twins suggest the role of epigenetic differences in androgenetic alopecia. European Journal of Dermatology, 2013, 23.1: 113-115.
ANASTASSAKIS, Konstantinos; ANASTASSAKIS, Konstantinos. Hormonal and genetic etiology of male androgenetic alopecia. Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders, 2022, 135-180.
SAKHIYA, Jagdish, et al. Prevalence, severity and associated factor of androgenetic alopecia in the dermatology outpatient clinic: A retrospective study. IP Indian J Clin Exp Dermatol, 2019, 5.4: 280-287.
ANSAI, Toshihiro, et al. Associations among hair loss, oral sulfur-containing gases, and gastrointestinal and metabolic linked diseases in Japanese elderly men: pilot study. BMC Public Health, 2009, 9: 1-6.
TRILISNAWATI, Damai, et al. Update treatment of male androgenetic alopecia. International Journal of Dermatology and Venereology, 2021, 33: 63-71.
WANG, Ya-Xin, et al. Association between androgenic alopecia and coronary artery disease: a cross-sectional study of Han Chinese male population. International journal of general medicine, 2021, 4809-4818.
CHOI, Gwang-Seong, et al. Long-term effectiveness and safety of dutasteride versus finasteride in patients with male androgenic alopecia in South Korea: a multicentre chart review study. Annals of Dermatology, 2022, 34.5: 349.